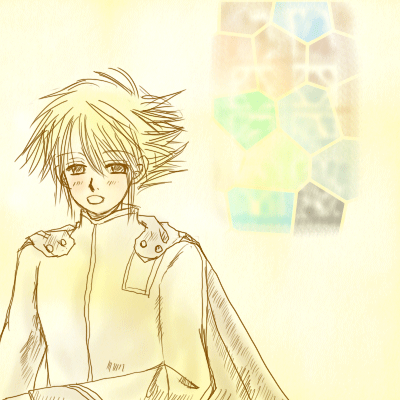
SW シリーズ拍手より再録
ドーム型となっている天井は高い。
ステンドグラスによって装飾されており、自然光を受けると天然の芸術となる。
首を真上に向けて見上げてみても、それだけでは視界に全ては入りきらない。
クラウドは見上げるのをやめて、視線を手に持っている本に落とす。
手に今持っているのは三冊。すぐそこにある机の上には四十冊以上の、古くて分厚くて大きな本がぎっしりと並べられていた。
ここはテンプルの書庫。
専門的な知識を得るには、最高の場所だ。
今テンプルでは旅立ちの季節。幼いパダワン候補達が、学ぶべき師ソルジャーと出会い、テンプルから巣立っていく日が、もう目の前まで来ている。
巣立ちの儀式は一ヶ月後。
ソルジャーという師を得た者たちは、巣立ちの儀式の後、テンプルを出ていく。
そしてソルジャーと寝食を共にして成長していき、将来は立派な次代のソルジャーとなるのだ。
クラウド・ストライフ。
テンプル最長在籍者である。
そして来月の巣立ちの儀式にも――出席する予定はない。
クラウドは手に持っている三冊を、元にあった場所へと分類して戻していく。
書庫整理は単なる雑用ではあるものの、誰でも出来るような簡単なものではない。
膨大な所蔵を誇る書庫の分類に精通するのは難しい。
余程の知識と根気がなければ難しいだろう。
クラウドはテンプルに在籍してからずっと、この書庫整理を担当してきた。
努力を惜しまないクラウドの知識は、司書の担当者にも劣らないのだ。
おまけに他にもいた書庫整理を担当してきた者達は、パダワンとなるべく毎年巣立っていくし。
結局在籍年数が長いだけ、クラウドの書庫整理も手慣れたものとなっていき、今や書庫のどこにどんな本があるのか全てを理解している。
毎年クラウドはこの書庫で、巣立ちの儀式のリハーサルを聞いてきた。
それは最年長者でありながら巣立てないクラウドに対する、テンプルの温情だったのだろう。
少なくともこの書庫にいれば、直接に巣立ちの儀式を見ることはない。
巣立ちへとはしゃぐ学友の間で、途方に暮れることもない。
手に持っていた本をきちんと書架へと戻すと、次に取りかかる。
今日は良い天気だ。
明るい陽差しは天井のステンドグラスを通り、澄み切った光に色彩をつけながら、書庫という空間へと降り注いでいる。
クラウドは書庫が好きだ。
他人との付き合いが苦手なクラウドは、物こそ言わないがどこか暖かい本の間に埋もれていると、リラックス出来る。
本は欲すれば欲するだけ貴重な知識を与えてくれるのに、人とは違いクラウドから何も奪おうとはしない。何かを強制されることもない。
続いて数冊の本をしまい込んだ後、クラウドは懐から一通の手紙を出した。
黄ばんだ安っぽい封筒は、共和国評議会神羅が直轄するここミッドガルでは流通していない粗悪なものだ。
そもそも手紙などという媒体は、今やほぼ使用されてはいない。
だがクラウドは安っぽい封筒を大切そうにおし抱くと、中からそっと手紙を取りだした。
この手紙は昨夜クラウドの故郷、ニブルから届いたものだ。
差出人はクラウドの母。
彼女はたった一人でクラウドの帰りを待っている。
手紙の内容は簡潔だった。故郷ニブルヘイムでの出来事ばかり。
隣の息子に嫁がやってきたとか、新しい集会場が出来たとか、ニブルヘイムでのありふれた日常ばかりだ。
母は一言もクラウドを気遣うような内容は書いてこない。
それこそが母の自分に対する気遣いなのだと、クラウドは痛いほどよく解っていた。
ふと光の角度が変わる。きっと雲が動いたのか。
安っぽい黄色の手紙に、ステンドグラスを通した輝きが当たった。
薔薇色の優しい光に染め上げられて、母からの手紙は花弁のように色づく。
――母さん…
親一人子一人で育てられてきたのだ。
その母の優しい気持ちがそのままに色づいたようで、クラウドは薔薇色の花弁を胸に抱きしめる。
――ごめん…今年もムリみたい。
ソルジャーになると言ってわがままで家を出たのに、どれだけ努力を積み重ねても、クラウドはテンプルさえ卒業できないのだ。
ソルジャーへの第一歩すら踏み出せない。
誰もクラウドのマスターにはなってくれない。
自分よりも年下の子供達は、マスターを得て、未来への希望で胸を膨らませて、巣立ちの儀式に臨むのだというのに。
巣立ちの儀式で新しくパダワンとなった子供は謳うのだ。
この世界を祝福する歌を。
誘うように光がクラウドの頭上に射す。
見上げるとドーム型の天井は、ステンドグラスの反射により、様々な色の光の洪水となっていた。
目を閉じて、クラウドはそっと歌い出す。
天使たちが 野辺にて
天より聖歌をうたいはじめたまえり
山々は木霊によって
いと甘美なるうたを繰り返す
いと高きところ 神に栄光あれ
元々は古い旧世界で祈りの前に謳われたものだという。
張りのある透明な歌声で、クラウドは色とりどりの光に包まれながら、そっと歌った。
書庫に来たのは用事があったからだ。
古い法令について、その運用の解釈の範囲を確かめにきたのだ。
本来ならば文官に命じるところだが、来月に迫っているという巣立ちの儀式に人員をとられ、その忙しなさに自ら書庫に赴くことを決めた。
忙しい所に仕事を言いつけるのをすまないと思ったのではない。
仕事は仕事だ。
どんなにヘビーだろうがハードだろうが、やってもらわないと意味がない。
セフィロスが嫌ったのは、自分の命令が正確に聞き届けられて果たされるかという部分でだった。
何度も同じ命令をするのは、完全なる無駄だ。
幸い時間も空いていた為、書庫にやってきたのだ。
書庫の前で誰かの気配を感じる。
どうやら先客がいるようだ。
神羅の英雄であるセフィロスに憧れる者は多い。
無礼に近づいてくる輩は手厳しく追い返すが、それ以外の、特にここテンプルでよくあるパダワンの卵たる幼い子供に憧憬の眼差しを向けられるのは、手厳しく追い払えない分、セフィロスはあまり好きではなかった。
そっと気配を殺して、必要な書物だけ抜き出して、そのまま戻るつもりだったのに――
書庫に滑り込んだセフィロスの動きが止まる。
――歌だ。
巣立ちの儀式で歌われる聖歌のひとつに違いない。
澄んだ声は静かな書庫に響く。声の美しさよりもセフィロスの動きを止めさせたのは、歌声に込められた切ない祈りであった。
歌声の主を捜すべく、そっと覗く。
書庫の天井は大きなドーム型となっている。
その真下、古く大きな本に埋もれた一角に、光が射し込んでいた。
ドーム部分の装飾しているステンドグラスを通った光である為、色は一色ではない。
色とりどりの、赤、青、紫、金、の光が、それぞれの輝きとなっており、少年を祝福しているように注いでいる。
輝きは少年の上に降り注ぎ、そして弾けていた。
少年の金髪で弾け。ふっくらした瑞々しい肌で、弾けて。
それは輝き自らが少年と戯れているようで。
――これは…
ソルジャーであるセフィロスの感覚が捉える。
少年の歌声と輝きが、螺旋を描きながら天へと戻っていく様を。
それはとても厳かである。
同時に神聖でもある。
思わずセフィロスの感覚が螺旋へと伸びる。
手を伸ばすような感覚で、触れてみようと試みたのだ。
と――セフィロスを感知して螺旋が方向を変えてきた。
ぐるりと取り囲むと、長い銀髪を擽っていく。
――マスター…
螺旋の中から少年の声がして、自分を呼ぶ。
ソルジャートップであるセフィロスだが、これまで一度もパダワンを持ったことなどなかった。
マスターなどと呼ばれたこともなかったのに。
――そうか!
そういうことか。
セフィロスは覚醒する。
そして彼は目の前の少年が歌い終わるまで、じっと耳を傾けた。
入室したセフィロスの姿を認めて、クラウドの目が限界まで見開かれていく。
きれいな青が大きく丸くなっていく様に、セフィロスは夢中になった。
そう――正しく夢中だ。
あの書庫での日からセフィロスのパダワン探しが始まったのだ。
金髪碧眼の少年。色は白い。歳はテンプル育ちにしてはとっている方だろう。
小柄ではあったが10歳以下には見えなかった。
そして何より、あの日あの時間に書庫にいた者は…
探し人はすぐに見つかった。
名前はクラウド。テンプル最年長在籍者。
成績優秀。真面目で勤勉。内向的でネガティブな側面があるにしろ、優秀なパダワンになれるのには、間違いがない。
これまで他のパダワンとなっていないのが不思議なほどだ。
例え年齢というハンディがあったのにしろ、クラウドの成績はそのハンディをうち消すのに充分だったのに。
テンプルの教官たちも、彼がこれまでどのソルジャーにも選ばれず、パダワンとならなかったのは、とても不思議だと口を揃えていたし。
少年の前に立ち、無垢な青い瞳で見上げられて、セフィロスは自分が柄にもなく緊張しているのだと悟る。
緊張の理由を考えてみれば明白。
――俺はこの子供に好かれたいのだな。
可愛い可愛い――俺のパダワン。
掌中の珠として、丹精込めて育ててやろう。
「クラウド――俺はセフィロスと言う」
「他の誰でもない。お前が良いのだ」
「どうか、俺のパダワンになってくれ――」
少年の頬が見事に上気した。
柔らかな薔薇色は、あの日少年が抱きしめていた、手紙の色と同じだった。
END
二人の出会い編でした。
| << BACK | HOME | NEXT >> |