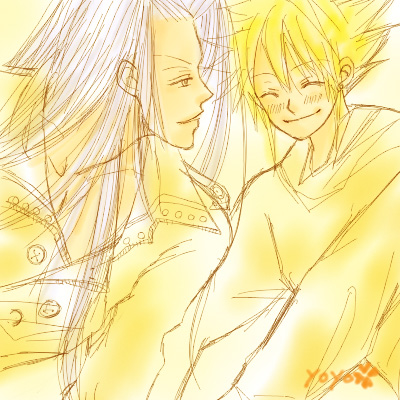
SW シリーズ拍手より再録
朝のコーヒーの香りを楽しみながら、セフィロスの視線は愛するパダワンから離れない。
特徴的な金髪を揺らしながら、パダワン殿は朝から大忙しの様子。
右へ行き、左へと移動して、キッチンに入ってひとつ作業を終えると、次に取りかかる。
リビングを出ていったかと思うと、すぐに手に荷物を持って戻ってきた。
そうして忙しなくしている間にも、クラウドはセフィロスを無視して放っているのではない。
ひとつひとつの行動のセンテンスに、セフィロスへと視線を向けてくるのだ。
セフィロスへの溢れんばかりの敬愛を込めながら。
共和国評議会神羅に属するソルジャートップであるセフィロスは、英雄と呼ばれている。
よって彼にどういう形にしろ尊敬や憧憬を向けてくる者は数多い。
自分に向けられてくるそのどれにも、これまでセフィロスは無反応でいた。
特に意識して反応しなかったのではない。反応する気にもなれなかったのだ。つまり反応する以前で終わっていたのだ。
有り体に言えば――他人の感情などどうでも良かったのだし。
それがこのパダワンだけは違う。
いつまでもクラウドから惜しみない敬愛を捧げられる、唯一の存在でありたい。
クラウドに会ってセフィロスは初めて己の存在意義というものを見いだしたのだ。
こうしてよく動く金髪の小さな頭を眺めていると、最初クラウドをパダワンとしたばかりの昔を思い出す。
あれはクラウドがテンプルの自分の部屋を引き払った時だ。
セフィロスはテンプルまでクラウドを迎えに行った。部屋の整理を終えたクラウドが部屋から出てくる。
「お待たせしました。…マスター」
マスター、――と呼ぶのがまだちょっと気恥ずかしいのだろう。
語尾は少し掠れて揺れていた。
セフィロスは「構わない」という意を込めて小さく頷くと、そのまま先に立って歩き出す。
後ろを振り向く必要はない。ちゃんとクラウドはついてきている。
そうやってテンプルの出口へと歩きながら、セフィロスは彼らしい無駄を省くやり方で、できたてのパダワンにいくつかの質問をした。
主にクラウドがこれまでに納め修行したことについてだ。
クラウドのテンプルにおいての成績は、セフィロスもちゃんと目を通している。だが良くも悪くもそれはあくまでも記録にすぎない。
セフィロスはクラウド自身からの話を知りたかったのだ。
「銃の成績が良いとあったが」
「はい。僕はまだ身体が小さいですので、剣よりも銃を扱う方が体力的に楽なようです」
「だが、剣の成績も悪くはなかった」
小柄なのはなるほどハンデなのだろうが、それを差し引いてもクラウドの剣の成績は悪いものではない。むしろ優秀の部類に入る。
「剣は好きです」
ですが、
「長時間ふるって戦うとなると…」
「そうか――体力が切れるのか」
こうして会話をしていると、クラウドはとても良い相手であった。
頭の回転が速い。それに実直である。
己を少しでも背伸びさせて良く見せようと言う下心がない。
セフィロスの質問に素早く対応して、なるべく飾らずに正直なところで返答してきている。
テンプルからの書類には、適正の欄に「対人関係が苦手である」とあったが、それはこの実直さが裏目に出ただけのことであろう。
クラウドの性格はむしろとても好ましいものだ。
こうやっていくつかの質問を繰り返している間に、セフィロスはふと違和感を覚える。
クラウドの声が遠くなったり近くなったりと、距離が一定でないのだ。
おまけに歯切れ良かったクラウドの物言いが、だんだんと息切れているようで。
セフィロスはそこでやっと足を止めると、背後を振り向いた。
クラウドは、確かにいた。だがパダワンにしたばかりの少年は、セフィロスの背後を小走りしていたのだ。
白い頬はバラ色になっている。息切れしているのは、走りながら返答していたからなのだろう。
小さな金色の頭は呼吸と同じリズムで揺れていた。
――なぜ、走っているのだ…?
あ、
――歩幅か。
セフィロストクラウドの身長差はかなりある。
もちろん足の長さも。一歩を踏み出すコンパスも。
おまけにセフィロスはソルジャーとして最高峰にいるのだ。軍人とは基本的に早足となる。その上基礎体力も比べものにならない。
セフィロスの一歩は、クラウドの一歩では追いつけない。
セフィロスは普通に歩いているつもりでも、クラウドにとっては小走りしなければ追いつけないのだ。
そしてまた、セフィロスはその類の気遣いをしたことがない。
クラウドの小走りの原因を理解したセフィロスが口を開くよりも先に、クラウドは必死になってマスターを見上げる。
「申し訳ありません、マスター」
「足が遅くて……もっと早く歩くようにします」
心中など考えるまでもない。
――マスターに嫌われたらどうしよう。
やめるなんて言われたら。こんなパダワンなんていらないって呆れられたらどうしよう。
悲痛な想いで彩られた青い眼差しは、これまでセフィロスが出会った何物よりも、彼の心を溶かすのだ。
セフィロスは何も言わず、そっとその手をパダワンへと差し出した。
「マスター…――」
差し出された大きな手と、セフィロスの顔を見比べてから、やっとクラウドは意味が解ったようだ。
おずおずとその小さな手を重ねてくる。
まだ子供の手だ。いくら修行をしているといえども、彼はまだほんの子供。
だがクラウドはただの子供ではない。セフィロスの、セフィロスだけのパダワンなのだ。
壊さないように包み込むように、その小さな手を握りしめる。
再び歩き始めてから様子を窺ってみると、小さな金色の頭はセフィロスト同じ速度で揺れていた。
あれから数年が過ぎた。
幼かった彼のパダワンも今や立派なパートナーだ。
セフィロスの方が、クラウドを頼っているのが本当のところ。
あと数年もすればクラウドも独り立ちするのだろう。セフィロスから離れてソルジャーとして生きていくのだろう。
そんな常識でさえ、すでにセフィロスは認められないでいる。
――どのようなことになってもクラウドは放さない。
これを狂気だというのならば、それも良かろう。
セフィロスはコーヒーを飲み干して朝食を終える。食器を重ねてキッチンへと運んだ。
これはクラウドと共に暮らすようになってからついた習慣だ。
シンクに食器を置いたセフィロスにクラウドが微笑む。
敬愛のこもった眼差しでセフィロスに笑いかけてから、彼はちょっと大人びた風に、
「良くできました。マスター」
このパダワンは本当に成長した。
セフィロスを誉められるくらいに、だ。
「ありがとう。マイパダワン」
セフィロスが長身を折ると、パダワンはマスターの銀髪の髪をそっと撫でた。
END
| << BACK | HOME | NEXT >> |