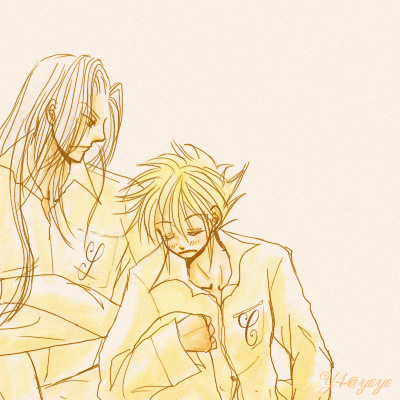
SW シリーズ拍手より再録
ソルジャー幼年学校はテンプルと呼ばれている。
古の言語Templum〜神聖なる場所〜より派生し、神殿、寺院を指す言葉だった。
神聖な場所とは、勉学を志し己を鍛え上げる場所でもある為、そこから“学院”と同じ意味で使われるようにもなる。
この世界のほとんどを掌握している共和国評議会、神羅が直轄するテンプルには、下は5歳から上は12歳の子供まで、現在83名が未来のソルジャーとなるべく基礎訓練を受け、集団生活をしていた。
現在テンプル在籍最年長者は、クラウド・ストライフと言う。
共和国エリアでも北にある、ニブルヘイム出身の少年だ。
彼が遅いスカウトを受け、テンプルにやってきたのが、11になったばかりの頃。
それから1年半以上が経ち、テンプル入学時には数名いた同年の子供達は、今は一人も残ってはいない。
クラウドは正にラストワン。最後の一人だったのだが……それももう今日でおしまい。
与えられているテンプル内の自室で、クラウドは夢見心地のままでいた。
ワンルームの狭い部屋は、この年頃の少年が生活するには充分な設備が用意されている。
バスルームは備えられており、キッチンこそないが、小さな机とベッドはあった。
どれも使い古されており新品ではないが清潔であり、メンテナンスも充分になされている。
ニブルという田舎で育ったクラウドにとって、この部屋は勿体ないほどの我が家だったのだ。
元々私物が少なかった部屋は、今は閑散としている。
小さな箱2つ分。クラウドの私物は全てこの中に収められてしまったから。
テンプルに来て1年と半分。クラウドは必死で訓練と勉強に励んできた。
人の倍どころか三倍は努力した。
元より遅いスカウトだ。訓練開始が早ければ早いほど、才能が開花しやすいとされているソルジャーにあって、11歳でテンプル入学となったクラウドは、遅すぎるも良いところだったのだ。
クラウドも充分自覚している。だからこそ努力を積み重ねるしか出来なかった。
成績は良かった。実技もペーパーもどれもテンプル記録を塗り替える出来であったが、いつまで経ってもクラウドのマスターは現れない。
周りもクラウドの優秀さは認めつつも、パダワンにはなれないだろうと。
このままテンプルに残り、教官への道を進まないか、と誘われてもいた。
クラウド自身諦めかけていたその時、奇跡は起こる。
奇跡――そうそれは奇跡としか考えられない。
クラウドのマスターが現れたのだ。
しかもその相手が相手だ。
――スゴい、きれいな人だった…
あんなきれいで逞しくて強い人物は、他にはいない。
小さな電子音がいきなり起こった。
夢見心地のままでいたクラウドの背筋が伸びる。
慌てて返事を返すと、あの人の声がした。
『クラウド――俺だ』
――サーだ!
「は・はいっ。今開けます」
転がり落ちるようにクラウドは自室のドアへと走り寄る。
端末を操作すると、ドアは開き、そこにいたのは信じられない美貌を持つ、神羅の英雄の姿であった。
サー・セフィロス。
神羅ソルジャーのトップに立つ英雄。
戦士として申し分のない鋼の肉体の上にあるのは、煌めく銀髪をなびかせた完璧なる美貌。
美しさと逞しさと強さを、そのどれもを最高レベルで遜色なく兼ね備えたセフィロスは、長い間ずっとパダワンを持たなかった。
それが――
「クラウド。用意は出来たのか?」
それが、その英雄が、クラウドのマスターになってくれたのだ。
ずっと憧れだった英雄のパダワンになるだなんて。
マスターとパダワンは寝食を共にする。
もちろん任務も、二人でコンビを組んで解決に当たるのだ。
この奇跡にクラウドは夢見心地のまま。とても現実だと信じられないままでいる。
返事もせず、ぼーっと自分を見上げている少年に、セフィロスは自然と笑みが浮かんだ。
この少年は己の魅力がどうセフィロスに作用するのか、自覚しているのだろうか。
12歳の少年は、まだ小さくて細い。身長は平均あるようだが、体重は全然足りない。
手足の大きさはそれなりにあるので、成長期になるとグンと伸びるのだろう。
共和国でも珍しい混じりけのない金髪と青い瞳。
寒いエリアで育ったからか。皮膚の薄い白い肌。肌の下の血管は、きれいに赤く血の色が透けて見える。
金色の睫毛に縁取られた青い瞳は、今こぼれんばかりに開いて、セフィロスを見上げているのだ。
見る見るうちに、頬がほんのりと赤く染まっていく。
その様子は過不足無く美しい。
「…クラウド?」
再び名を呼ばれて、やっとクラウドは我に返った。
大きく瞬きしてから、視線を逸らす。
「はい…、あの……用意は出来ました」
殺風景な部屋にあるふたつの箱にセフィロスは目を留め、
「これか?」
「はい」
少なくはないのか?
「これで、荷物は全部か?」
「はい――」
何度も念押ししてくるセフィロスに、クラウドは不思議そうだ。
セフィロスに疑問を抱いているのではなく、自分がセフィロスの気に障ることをしてしまったのでは、と思い、この短い間の遣り取りを反芻する。
満足な受け答えが出来なかった。
しっかりとした意思表示も出来なかった。
元より内向的でネガティブなクラウドは、自分のマイナスポイントしか思い浮かばない。
――サーの気に障ることがあったんだ。
たぶん、自分の行動の全てが。
薔薇色だった頬が、色を失う。
ぼうっとした熱っぽい表情が、硬く強張り、クラウドの青い瞳は伏せられてしまう。
いきなりのこの変化が痛々しくて、セフィロスは柄にもなくうろたえた。
もっとも、表面上はいつものクールさのままだから、誰もセフィロスが狼狽しているなどとは思うまいが。
他人の行動で心を揺さぶられ痛々しく感じ、ましてや狼狽するなど、クラウド以外には有り得ない。
「どうした?気分でも悪いのか?」
自分を気遣ってくれる思い遣りを感じ取り、クラウドは小さく首を振った。
幼子のようなあどけない仕草に、セフィロスは己の内に湧いてくる圧倒的な感情を抑えられない。
それはシンプルでいて、当たり前すぎるが、だからこそセフィロスには複雑で無縁だった感情。
この少年を大切にしてやりたい。
誰にも傷つけさせたくはない。
傷ついて欲しくはない。
自分のこの手で護ってやりたい。
立派に独り立ちしても、側に置いておきたい。
初めての感情によって振り回される己を、セフィロスは許した。
青ざめて首を振る少年の前に跪き、未成熟な身体を抱きしめたのだ。
「――っ」
驚きで身を固くする少年の髪を、なるべく優しく撫でていく。
何度か繰り返しているうちに、少年の身体から硬さが取れた。
「クラウド――」
透明感の強い白い耳朶に囁く。
「俺は何かお前にしたのか?」
「いいえ!そんな…」
「サーが悪いんじゃないんです」
「僕が…僕がちゃんと出来ないから…」
悪い?
「クラウド。お前に悪い所など何もない」
「でも…荷物が少ないって…」
可哀想に。この少年は過敏になっているのだ。
ほんの些細なことすらも、己が悪いと責め続ける。
もっと素直になって欲しい。セフィロスの言葉によって怯えては欲しくはない。
だからセフィロスは言葉を惜しまなかった。
言葉など最低限で充分だと思ってきたが、クラウドに惜しむものは何もない。
「確かに少ない荷物で驚いたが、悪いことではない」
「これからは、俺とひとつづつ揃えていこう」
必要なものも。
必要でないものも。
これからの時間を、二人は共に過ごすのだから。
低く甘く睦言のように囁かれ、クラウドは歓びに震える。
他人にこれほどしっかりと抱きしめられるのは、母親以外には初めてだ。
父親を知らないクラウドにとって、男にこうされるのも初めてのこと。
母親とは全然違っている、逞しくてどこまでも広い身体に己を預けるのは、とても心が落ち着く行為だった。
――このままずっとサーといたい。
憧れだけではない。
この人の隣に立てる栄誉を、誰にも渡したくはない。
クラウドが初めて感じる、強い欲望だった。
今度こそは間違えないようにと、クラウドは恥ずかしさを超えて、セフィロスに応える。
「はい。サー」
ククク、とセフィロスが笑う。
ピッタリとくっついている逞しい身体も小さく揺れた。
「違うだろう。マイパダワン」
「…はい、マスター――」
――ああ、それで良い。
こうして二人は名実共に、マスターとパダワンになる。
エアスピーダーによって連れてこられたセフィロスの住居は、ミッドガル高級住宅エリアの一角にある高層マンションであった。
そこの最上階。フロアー全部がセフィロスの専有フラットとなっている。
最新式設備をふんだんに使ってあるマンションは、広くモダンで華美にならないセンスがあった。
クラウドの部屋もちゃんと個室が用意されている。
これまでのとは比べものにならない上等なベッド。机も大きく、どれも新品だ。
物欲が極端にないクラウドだが、部屋やベッドや机の豪華さよりも、これだけの品物を自分の為に揃えてくれたセフィロスの優しさに心打たれる。
胸がツンとして、思わず涙ぐみそうになって立ちつくすクラウドの様子に、セフィロスは慌てる。
「その…俺の部下がパダワンを迎えた時を参考にして揃えたのだが――」
やはり、クラウド自身に選ばせた方が良かったのだろうか。
「気に入らなければ、他のモノを揃えよう」
「いいえ――いいえ、マスター」
振り返ったクラウドには笑顔があった。
セフィロスの気持ちは一気に上昇する。
クラウドの一喜一憂を案じ、振り回されるなど――だがこんな自分はとても好ましい。
「僕とても嬉しいんです」
「ありがとうございます。大切に使います」
セフィロスがパダワンを迎えることを、一番祝福してくれた部下の言葉が浮かぶ。
(良いもんだぞ。パダワンってのは)
そいつは気の強い女の子のパダワンを持っている。
変わった女の子で、一見優しげでありながらもその実言動には容赦がない。
セフィロスからすれば“変”としか言いようがないのだが、それでもそいつは自分のパダワンの尻に敷かれて、きつい言葉を投げられて喜んでいる。
(何でもしてやりたいっていう気持ちになるんだ)
――本当にそうだな。ザックス。
そして、パダワンに振り回される自分は、悪くない。
と、そこで思い出した。
「そう言えば、その部下がお前にプレゼントを用意していたな」
「僕にですか!?」
「それだ」
ベッドの上にある薄い箱。
確かにプレゼントというだけあって、箱にはブルーのリボンが掛けてあった。
クラウドはセフィロスを仰ぎ見る。
それに答えてやって、
「開けてみろ」
「はい」
クラウドは慎重に箱を手に取ると、丁寧にリボンを解いていく。
箱はとても軽い。重さでは中身がなんなのか想像が付かない。
箱を開けて、中を覗いて、ちょっと小首を傾げた。
「なんだった?」
「それが――」
クラウドが差し出した箱にあるのは…
「服か?」
それはどう見ても服のようだ。
折り畳まれて梱包されているから、襟の部分しか見えないが、普通に身につける服にしては、ゆとりがあるように見える。
クラウドは箱から取りだして、目の前で広げて見せた。
「あっ!」
「これ、パジャマですよ。マスター」
左胸の飾りポケットに刺繍が施してある。飾り文字のC。これはクラウドのネームだ。
「もう一着あります」
同じ上品なベージュの色味。同じ生地。同じデザイン。だがサイズは全然違う。クラウドのモノよりもかなり大きい。
左胸ポケットにある刺繍の文字は、飾り文字のS。
「これ…マスターのですね」
――ペアパジャマなんだ。
こんなのを僕だけじゃなくて、マスターにも贈るなんて、
――変わった部下なんだなあ。
マスターと仲が良いソルジャーなんだなあ。
ふふ、と思わず笑みが零れてしまう。
その笑顔を見て、セフィロスは決めた。
ザックスのつまらない冗談であるが、クラウドが気に入っているのであれば、セフィロスに異存はない。
何より、初めてクラウドが幸せそうに笑ってくれたのだ。
ザックスのバカには普段飽き飽きしているが、今回だけは許してやろう。
ペアとなっているパジャマを見て微笑んでいる、金色の頭に手を置く。
「荷物の整理が終わったら風呂に入ってこい」
「ちゃんとそのパジャマを着るんだぞ」
「……!?」
本当ですか?マスター。と可愛らしい顔が、その青い双眸が物語っている。
きょとんとした顔は、どこか人形めいた少年を幼く見せた。
もっともっと可愛がってやろう。
ザックスがやつのパダワンを可愛がる以上に、この世で一番俺がクラウドを可愛がってやろう。
甘えさせて、可愛がって、自分が持つ剣技や知識を全てこの少年に与えてやろう。
見返りなどいらない。
ただずっと「マスター」と呼んでくれさえすれば充分だ。
「着てみたら、ちゃんと見せてくれ」
――良いな。マイパダワン。
「…――はい、マスター」
小さいが幸福を滲ませる声で、クラウドは頷いた。
風呂上がりにちゃんとパジャマを着てくれたクラウドは、とても可愛らしかった。
「なんか、照れます」
頬を染めるパダワンの髪に触れる。
長く伸ばされた髪。パダワンになるとその証としてブレイドを編み込むのだ。
テンプルにいる子供達は、ブレイドを編めるように髪を伸ばす。
肩にまで伸びた金髪をそっと掬った。
手触りの良い髪は、見た目の奔放さを裏切って、セフィロスの手に素直に馴染んでくる。
「明日、ブレイドを編んでやろう」
「はい。マスター」
明日も明後日も一ヶ月後も、一年後も、その先も。
セフィロスがマスターで、クラウドがパダワンでいる間は、二人は同じ時に眠り、同じモノを食べ、同じ視線で見つめるのだ。
あまりにもじっと見つめられて、クラウドは頬を染めたままプイっと下を向く。
そのふっくらした薔薇色の頬に、セフィロスはキスを贈った。
END
拍手より再録
確かY子のイラストを見てSWパロを書くというゲームだった気がします。B子さんが↑のイラストで非常に困った記憶がかすかにあります。
| << BACK | HOME | NEXT >> |