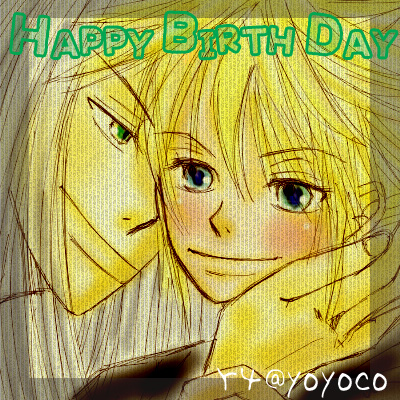
SW シリーズ07クラ誕MEMO連載より
徐々に海の色が変わっていく。
港では不純物のいくらかは混じった灰色がかった藍だったものが、今は抜けるような青へと。
遠くの深い場所には潮の流れがあるのだろう。そこだけはなんとも不思議な碧の藍だった。
元より山育ちのクラウドにとって、海とは神秘の場所だ。
生き物を育む懐を備えつつも、一面非常に命を奪っていく様は、海も山も似てはいる。
決定的に違うのが生命だ。
山は植物、木や草を生み出す。
海は海に住む魚やその餌となるプランクトン。もっと大型のほ乳動物を生み出し育てるのだ。
太陽の光を浴びて水面が輝く。小型船のスクリューから弾ける白い水しぶきは、長い線を描いて海へと消えていく。
クラウドはさっきからずっと飽きることなく、この光景に心奪われていた。
二人がいるのはコスタ・デル・ソル。
神羅がが統治するエリアのひとつだ。
このエリアの特徴は、溢れんばかりの海洋資源。
なにせ陸地と海の対比が8:2。おまけにまともな陸地はほとんどなく、小さなシティがやっと出来るほどの島々がエリア中をくまなく連なっている。
この陸地面積のなさはコスタデルソルにひとつの道を選ばせた。
すなわち、観光エリアとしての道を。
大きな陸地がないのだから重工業は発展しない。
頼みの海洋資源もそれほどは恵まれておらず、むしろ神羅は美しいエメラルドグリーンの海と、海に住む生物たちに着目したのだ。
海洋リゾートエリアとして開発。思惑は見事に的中。コスタ・デル・ソルは一大リゾートエリアへと発展した。
潮の流れをじっと観察していると、魚影が見える。
思わず身を乗り出したクラウドを、優しい声が止めた。
「マイ・パダワン−−」
「俺を置いて海に引きずりこまれるな」
敬愛すべきマスターの茶化した物言いに、クラウドは魚影から目を離す。
「マスター!」
なんの迷いもなくセフィロスに駆け寄ってくる少年を、彼は長い腕を広げて迎える。
少しだけ恥ずかしそうな弟子の小さな肢体を、マスターはそっと抱きしめる。
「海は好きか?」
−−クラウド。
声だけでクラウドを擽っているようだ。
これが成熟した相手ならば、そのまま前戯ともなったであろうが、クラウドはまだ子供。
セフィロスの腕の中でくすぐったそうに身を捩るだけ。
「はい。マスター」
「僕は山育ちなので、海にはとても興味を感じます」
なにより、
「マスター。ありがとうございます。こんな素敵な所に連れてきてくださって!」
いつもは己の感情を隠す傾向にある少年だが、余程コスタ・デル・ソルの海が気に入ったのだろう。
白い頬を紅潮させて、見上げてくる様子は、とても愛らしい。
目の中に入れても痛くない弟子の様子に、英雄は目を細めた。
金髪が太陽を浴びて豪奢に輝く。
その輝きごとをセフィロスは愛でた。
神羅の英雄、マスターセフィロスの名はまさに全エリアに轟いている。
長い間自分のパダワンを持たなかったセフィロスだが、二年前にある少年を選ぶ。
それが、クラウドだった。
それ以来セフィロスは、己自身よりも遙かに大切な宝物を手に入れたのだ。
今回珍しくセフィロスは休暇を手にすることになる。
クラウドをパダワンにしてから初めての、長期休暇だ。
休暇の期間はなんと一ヶ月。この間よほどのことが無ければ、任務に呼び出されることはない。
セフィロスとクラウドの二人は、自由を謳歌出来る。
長期休暇が決まってすぐ、二人は共に過ごすと決めた。一ヶ月の間中ずっと、だ。
マスターとパダワンの多くは、短期休暇は次の任務の都合上もありだいたい共に過ごすことになるが、長期休暇ともなるとその全ての期間を共に過ごすのは少ない。必ず別々にとる期間が出るのだ。
だがセフィロスにはそのような選択肢などなかった。休暇と聞いてすぐ考えたのが、二人で過ごせる場所。
クラウドと二人きりで。なるべく他人が立ち入らない場所で休暇を送る事が出来たとすれば、どれほどに充実することか。
例えミッドガルであろうと、クラウドと二人きりで居られるとすれば、そこは正しく天国ともなろう。
セフィロスは自覚し認めているくらい、己のパダワンの少年を溺愛しているのだ。
もちろんミッドガルで二人きりで過ごすなど不可能。
そこでセフィロスは明晰な頭脳で考える。そしてパダワンに提案したのがここ、コスタ・デル・ソル。
神羅統治エリアの中で最も有名なリゾート地。
クラウドの瞳と同じ色を持つ、水のエリア。
任務では何度か立ち寄ったことがあった。だがそれは主にトランジットの短い間だけとか、小型船の燃料補給の為だとかで、クラウドはいつも発着場の内側からガラス越しでコスタ・デル・ソルの海を眺めていただけだったのだ。
海を眺めるその横顔は、実年齢よりも幼かったのをセフィロスは記憶に刻みつけていた。
その時幼い横顔に思ったのだ。いつかきっと休暇でコスタ・デル・ソルに連れてきてやろう、と。
ミッドガルでセフィロスはクラウドと暮らしている。
クラウドがこの空間にやってくるまでは、ここはただの箱でしかなかった。
神羅が英雄に与えた、広くて豪華な最新式の箱。
だがパダワンがやってきてから、ここは家に変貌したのだ。
家に帰ると心が安らぐ。人ならば幼い頃に知る当たり前のようなこんな実感でさえ、セフィロスはクラウドと暮らすようになってから知ったのだ。
この日は二人珍しく別行動をとっていた。幼い年齢のパダワン達は、定期的にマスターと引き離され、様々なテストやカウンセリングを受けている。
マスターに虐待を受けていないか。
きちんとした生活を送っているのか。
しっかりと指導を受けているのか。
ソルジャーとしての能力など。
事細かに神羅はなんでも知りたがる。
クラウドよりも遅く帰ってきたセフィロスを、パダワンの少年はいつものように玄関スペースまで出迎えた。
「おかえりなさい。マスター」
料理をしてくれていたのだろう。
抱き寄せた小さな身体からは、食欲をそそる匂いがする。
「ただいま−−」
丸味の残る滑らかな頬に口づけると、やはりそこには食べ物の匂い。思わず歯を立てた。
「うわっ」
「噛むなんて酷いです…」
軽くしか歯を立てていないから傷などついていないが、クラウドは思わず頬を押さえて半身だけ退く。
少年はまだ幼い。他の同じ年頃の少年少女と比べても、やはり幼い。彼には性愛など理解出来ないのだ。
−−今はそれでいい。
この最愛のパダワンはまだまだ子供であって欲しい。
出来ることならば永遠に子供のままで、自分のパダワンとして生きて欲しいのだが、これはセフィロスのエゴイスティックなわがまま。
「すまない。美味そうな匂いがしたのでな」
「マスター。そんなにお腹が空いているんですか?」
微妙にズレた遣り取りとなったが、セフィロスはそれすらも楽しむ。
「クラウド−−休暇をとることになった」
「はい」
と返事をするクラウドからは、休暇という喜びはない。
それもその筈。セフィロスは英雄なのだ。そのセフィロスのパダワンとなり幾度かの休暇を過ごしたが、それはどれも”きゅうか”という言葉からはほど遠いものばかり。
必ずなにかが起こって〜それも大抵大事件ではなく、神羅幹部のわがままからだった〜休暇は途中で返上せざるをえなくなる。
マスターを深く敬愛するパダワンとして、クラウドはまともな休暇をとっていないセフィロスが心配だった。
だから今回もこれまでの休暇と同じ、というニュアンスしか持てなかったのだ。
キッチンへと背中を向けるパダワンに、
「長期休暇だ」
心中にんまりほくそ笑んでセフィロスは言葉を投げる。
「え!?」
「一ヶ月。まるまるフリーだ」
「マスター!本当ですか!?」
クラウドの瞳が大きく見開かれる。きれいな円形となった瞳の青は今にもこぼれ落ちそうだ。
弟子を驚かせたのに満足しつつ、セフィロスは続ける。
「二人でコスタ・デル・ソルに行かないか」
「無人島にコテージを借りよう」
「そこで一ヶ月二人きりで過ごすというのはどうかな?マイパダワン」
目を大きく見開いたポーズのままクラウドは絶句している。
無人島と言っても観光としてちゃんと開発されたものだ。
水道電気の設備は万全。二人が暮らすには問題はない。
コスタデルソルには小さな島々が点在している。一周5キロほどの小さな島にセフィロスは目星をつけていたのだ。
そこは南国の木々の真ん中に一軒のコテージがあるだけ。他には何もない。エメラルドグリーンの海に囲まれた楽園。
かといって小型船さえ出せば、30分ほどで生活物資が手に入る島にたどり着けるし、不便はない。
セフィロスの説明を全て聞き終えたクラウドは、まず大きく深呼吸をひとつ。
紅潮した白い頬はまるで水蜜桃だ。きっと無垢な甘い匂いをしているに違いないと、セフィロスは思う。
「…マスター」
「ありがとうございます…」
マスターを見上げる瞳には、喜びの結晶があった。セフィロスがこれまでに巡り合った何物よりも、美しく貴い結晶だ。
その煌めきにセフィロスは満たされる。
「僕…とても嬉しいです」
「そうか」
これまでにない、最高の休暇となるに違いない。
休暇に入ったセフィロスとクラウドは、任務に使う専用小型機ではなく、民間の大型機でコスタ・デル・ソルに入る。
そこから小型のクルーザーをレンタル。二人で海に乗り出したのだ。
予約名はすべて偽名。全くの架空名義ではなく、神羅に所属している実在の人物名だ。何か不可抗力な出来事が起こっても対処は万全なのだ。
リゾートらしいラフな出で立ちのセフィロスは、特徴的な瞳はサングラスで、髪はひとつに束ねている。
変装ともいえない簡単なものであったが、それがかえって幸いしたようだ。小型クルーザーに乗り込むまで、誰もセフィロスだとは気づかなかった。
乗り物の運転はたいていクラウドがする。乗り物に弱いクラウドは、運転をしなければ酔ってしまうからだ。
港からクルーザーを駆り出してから30分。港近くの入り組んだ地形がすぎた頃、クルーザーは自動操縦となる。
目的に無人島まではあと小一時間ほどか。波も穏やかで安定した海の美しさは、クラウドに乗り物酔いを忘れさせる。
英雄セフィロスの名を汚さぬようにと、普段はことさら大人びた態度をとるクラウドだったが、海に心奪われて、船中をぐるぐる回っている様子は、年齢より幼いものだった。
一時たりともじっとしていないパダワンの様子は、それはとても愛らしいものだが、やはり一番良いのは己の腕の中で見上げてくる様だ。
セフィロスは両手を広げて、素直に飛び込んでくるパダワンを収めてしまうと、拘束を感じさせない微妙な力加減で抱きしめたまま離さない。
自分が動き回らないように拘束されているだなんて、クラウドは思いもよらないのだろう。
遠くに比較的大きな島が現れた。その周囲の海の色の不思議さに全身で驚き、
「マスター。なぜあそこの部分の海の色はあんな風に変わっているのですか?」
顔ごとで敬愛するマスターを見上げる。
−−やはりこの体勢が一番落ち着くな。
こうやって信頼と共に見上げてくる少年の姿は、セフィロスだけの特権だ。
「珊瑚礁があるのだろう」
「珊瑚!」
「あんなに広い珊瑚礁があるのですか!」
「そうだよ、マイパダワン」
観光エリアであるコスタデルソルは、自然に満ちている。
神羅の開発も自然を考慮したのものしかなされていないため、流石に手つかずの大自然とはいかないが、むしろ開発の行き届かない不便さをも、リゾートの売り物としているのだ。
「珊瑚は初めてか?」
「はい。テキストの写真では見たことがありますけど…」
「俺達の過ごす無人島の近くにも、あれほどの大きさはないが、小さな珊瑚礁があるそうだ」
「見られるんですか!?」
「珊瑚礁は浅瀬にある。潜ればいいだけだ」
連れていってやろう。
何せ一ヶ月あるのだ。時間は充分にある。
「マスター!」
太陽の光を浴びて、少年は一際輝く。
「すごく楽しみです」
自分を拘束する腕に、そっと小さな手を乗せた。
目的地の無人島まであと僅か。マスターと弟子は二人寄り添ったまま、海を見つめていた。
幸せだったムードが緊張に変わったのは、セフィロスがある波動を感知したから。
それは魔晄−−セフィロスには馴染みのザラついた感触は、一言で言い表すならば”凶”か。
神羅の調査によると、コスタ・デル・ソルには、魔晄エネルギーは認められていないというのに。
だがこれは明らかに、
−−魔晄だな…
全身の筋肉が緊張する。
抱きしめられて密着したままのクラウドは、マスターの戦闘態勢になった筋肉を感じ取る。
「マスター…?」
ここで、クラウドも魔晄エネルギーを察知した。
「…マスター」
少年の声が緊張で低くなる。
クラウドとてパダワン。魔晄がない筈のこのエリアで、これ程強い魔晄を感じ取る意味は承知している。
この強さ。これは単に”何かに魔晄が付着した”とか”魔晄を使用した何かがそこにある”というのではない。
この魔晄は塊だ。つまり魔晄の鉱脈があるか…。もしくはとても強く魔晄の影響を受けた、かなりのモンスターが生息しているか…、だ。
神羅の調査ではそのどちらもコスタ・デル・ソルエリアには、存在しないことになっている。
また該当する目撃情報もない。
「わかるか−−クラウド」
「はい。強い魔晄エネルギーです」
ソルジャーである以上、いくら休暇だからといえども、魔晄となれば話は別。
その正体を見極めなければならない。
「13時の方向だ」
「はい。そちらに向かいます」
クラウドは操舵室へと戻る。自動操縦から手動へと切り替えて、魔晄エネルギーの場所へと向かうのだ。
セフィロスはクラウドに案内すべく、小型船の舳先に立った。
長い銀髪が海の風になびく。360度見渡せる美しい海の楽園が、セフィロスの前に広がっている。どこにも魔晄の不吉さは見あたらないというのに。
インカムを装着したその時だ
(−−)
何かが、セフィロスに触れた。
それは言葉ではない。少なくとも、セフィロスの知る言語ではなかった。
ハッと操舵室にいるパダワンを振り返る。クラウドもすでにインカムを着けているのを確認して、
『聞こえたか?』
『はい…マスター…』
『誰かが、話しかけてきました』
クラウドはセフィロスと同じ感覚を持っている。さすがに、マイパダワンは優秀だ。
魔晄エネルギー発信源までは、そう遠くはない距離であった。長くはない移動の間でさえも二人は何度も何かに触れられていた。
無論実体ではない。
魔法とも少し違う。
マテリアとも、やはり違うような気がする。
クラウドだけではない。セフィロスも「違うだろう」と言っているのだから、これは確かだ。
−−だとすれば…
−−なんだろうか?
消去していくと、何も残らなくなる。
パダワンになる為テンプルでの修行期間が短かったクラウドは、その分の遅れを補うべく、貪欲に知識を吸収していった。
英雄と讃えられるセフィロスのパダワンになった後は、テキスト教本にはなかった様々な現象に遭遇してきたのだ。
己を過小評価しがちなクラウドはわかっていないが、結果このパダワンの知識量は神羅でも有数のものとなっている。
正しく、今向かおうとしているのは、未知との遭遇である。
未知を目の前にしてクラウドの心は、少年らしく揺れる。
好奇心と、未知と遭遇出来る幸運と、そして訳の解らないモノに対する原始的な不安と。
揺れる感情を沈める魔法をクラウドは知っていた。
それは、
−−マスター。
敬愛している英雄だ。
変哲のないレンタル小型船の舳先に立つ後ろ姿をじっと見つめる。
長い銀髪は風になびいていても見事に乱れない。いや、乱れそのものさえも、計算しつくされた芸術のようだ。
−−きれいだなあ、マスターって。
まるで、夢そのものだ。
パダワンになる前も、セフィロスの姿は雑誌や映像で知ってはいたが、実際にこれ程までに圧倒的な美貌だとは想像さえもしていなかった。
男でも”美”という言葉がこれ程似合うなんて。
神羅にやってくるまで、クラウドの世界は確かに狭かったが、それでも美しいものはあった。
例えば、冬の氷。結晶となった樹氷。光に照らされる雪山。
真夜中、深々と降り積もる雪、雪、雪。全てを白く覆い隠していくその様。
だがクラウドがこれまで美しいと感じたどれよりも、セフィロスは美しく強く、そしてどれにもカテゴライズされない存在感がある。
セフィロスは特別なのだ。特別すぎる。
セフィロスはセフィロスなのだ。それ以外でもそれ以下でもない。
人でもないのでは−−クラウドは心の中でそう信じている。
人ではなく、かと言ってもちろんモンスターでもない。
セフィロス、という独立した種なのだ、きっと。
ソルジャーの象徴として憧れていたセフィロスは、パダワンとなり共に暮らし、誰よりも身近な存在になってからも、色褪せることなどない。
むしろよりいっそう、セフィロスの偉大だを痛感するばかりなのだ。
強い−−これは当然解りきっている。
賢い−−これも当然すぎる。
優しい−−情愛深くて豊かだ。心の有り様が広い。
パダワンになってみて、身に染みるほどにわかった。
セフィロスとは真に偉大なソルジャーなのだ、と。
−−マスターの為になるのならば、僕はなんでもする。
クラウドの秘密の誓い。
セフィロスへの尊敬と思慕を噛みしめていると、不安などなくなってしまう。
一人ではない。どんな未知が待ち受けていようとも、セフィロスがいる。
船の舵を握り直した時に、また、何かが触れていった。
数瞬だけ遅れて、インカムからマスターの声が流れてきた。
『クラウド−−船を停止しろ』
『はい。マスター』
すぐに船を停止させると、操舵室に立てかけてあった正宗を持ち、マスターの元へと駆け寄っていく。
「マスター。これを」
「ありがとう、クラウド」
左手で正宗を受け取ると、彼は優しくパダワンに微笑む。
セフィロスが愛しいパダワンにだけ見せる、豊かな微笑みだ。
「クラウド。お前はここで待っていなさい」
「っ!」
僕も一緒に−−と叫びそうになるが、目的の場所はこの海の底だ。
なんの装備も用意していないクラウドなど、きっと辿り着けないだろう。
辿り着けたとしても、足手まとい以外に何者でもない。
クラウドは唇を噛みしめて、付いていきたい気持ちを押さえ込む。
「…マスター。僕、ご無事をお待ちしています」
クラウドの心中など解っているのだろう。セフィロスは少年の清らかな両頬に、そして額に口づけて、
「絶対にお前の元に帰ってくる」
「はい。マスター」
舳先からそのまま海に飛び込んでいく後ろ姿を、クラウドは静かに見送った。
海面から見ているよりも、海の中は素晴らしく澄んでいる。
海水は大気のようで、泳いでいるのか、飛んでいるのか、区別がつかないくらいだ。
揺らめく海面の動きに合わせて、光が煌びやかに屈折する。
文句の着けようのない素晴らしい光景だが、ただひとつ裏切るモノがあった。
−−魚がいないな。
そう。何もいない。
泳ぐ魚もいなければ、海に住む他の生き物の気配すらない。
大型の海獣たちほ乳類もいない。
さっき小型船から覗き込んでいた時は、魚影があった。
位置は少ししか移動していないというのに、差は歴然としている。
−−やはり、魔晄が原因か…
それにしては、やはりおかしい。
万が一、ここの海底に魔晄エネルギーがあったとしよう。
だとすれば、少なくともこの海域には魔晄による異常が起こっている筈。
生態系も異常を示し、魚などもモンスターへと変貌して然るべきなのだ。
それがどうだ。生き物の気配はないものの、海は至って平穏。異常は見受けられないではないか。
セフィロスは警戒をしながらも、エネルギーの源に向かって潜っていった。
ソルジャーの身体能力は、人のそれを凌駕している。
ソルジャーの中でも一番能力の高いセフィロスは、正しく人間以上だった。
何の装備もない素潜りでも、20分以上酸素を必要とはしないでいられる。
大きく逞しい腕で水をかき、長く力強い足で水を蹴ると、海底はすぐ見えてきた。
−−あれだな。
考えるまでもなく、はっきりとしている。
そう深度は深くはないが、やはり届いてくる光は少なくなっている。
ぼんやりとした海の中に、一際輝く海ではない青い輝き。
一目でわかった。この輝きは自然のものではないのだ、と。
セフィロスはこの輝きから強い意志を感じ取る。感じ取った意志は船上にて、自分とクラウドに触れてきたものと同じだったのだ。
輝きの傍へと向かっていると、また、何かが〜青い輝きだが〜触れてくる。
(……)
やはりセフィロスの知る言語ではないが、距離が近くなったからだろうかその意図だけは今度ははっきりと察知できた。
(あなたじゃないのに…)
訳すなら、こうだ。
(どうしよう)
(どうしよう)
(この人じゃないのに)
(この人は呼んでない)
傍に近づくにつれ、意志ははっきりと聞こえてくる。
輝きは海底に偶然できた、石と石の間にちょこんとあった。
まるで誰かがそこに安置したように。
−−石…
いや、
−−マテリアに近いものなのか…
(石と同じにしないで)
(そうよ)
(そうよ)
(私達はそんなモノじゃないわ)
さざめく声にセフィロスは己の意志を向ける。
(ならば、お前はマテリアなのか?)
(マテリア!?)
(何それ?)
(何かしら?)
(何かしら?)
どうやら、マテリアという概念はないらしい。
(それってきれいなの?)
(とってもきれいなの?)
(私達をひとつに出来るくらい、きれいなの?)
(あの子みたいに…)
あの子−−とは、もしや。
(お前が言っているのはこの子のことか)
記憶からクラウドの映像を取りだして、送ってみると、反応は顕著であった。
(そうよ!)
(この子)
(この子があの子)
(きれいだわ)
(なんてきれい)
(やっぱりきれい)
(この子なら、私達ひとつになれる!)
(ひとつになりたいの)
(やっと見つけたのに…)
(せっかく呼んだのに)
(あの子じゃなくて、あなたが来るなんて)
(あなたじゃダメなの)
(私達をあの子に会わせて)
セフィロスに向けられる意志は、ひとつではなかった。
いや、正確に言うならば、ひとつの意志にまとまってはいないというべきか。
源はひとつでしかないのだが、いくつかに分化しているらしい。
(ひとつになるとはどういうことだ?)
セフィロスの投げた疑問を受け、意志たちは一瞬だけ静まりこんだ。
そして、
(私達、昔はひとつだったの)
(私達、星の欠片だったのよ)
星の欠片だったと言うのならば、確かに魔晄やマテリアに似ているのも頷ける。
イメージが直接流れ込んでくる。
大きく漂うひとつの塊から、不意にはじき出されてしまった小さな欠片。
欠片は長い年月の間に、寂しさを覚えてしまう。
元々は大きな塊だったのだ。そのころがとても恋しくて。
寂しくなった欠片は、己の中に別の己を創造していった。
虚しい創造を繰り返して、もう元のひとつには戻れなくなってしまう。
そして得たのは−−ひとつの欠片に戻りたいという願いだった。
(私達だけでは、ひとつには戻れないから)
(戻してほしいのよ)
(それには”きれいな”意志が必要なの)
(やっと見つけたわ)
(きれいな子)
(きれいなこの子)
(きれいなあの子)
(この子がいたら、私達ひとつに戻れる)
(だからあなたじゃないの)
(この子がいい)
(あの子がいい)
(連れていって)
(連れていって)
(私達を連れていって)
複数の意志に分裂してしまっているからなのか、まるで幼い子供がダダをこねているようだ。
しきりに「クラウドの傍へ」とわめき続けているばかり。
瞬きすら惜しんで、クラウドはマスターが潜っていった海面をじっと見つめている。
臨戦態勢はとうにとれていた。
マスターに何か不足の自体が起こったとしたら、クラウドはすぐに助けに向かうつもりだ。
英雄と呼ばれるセフィロスを助けられるなんて、考えてはいない。
だがせめて自分が時間稼ぎにでもなれば、降りかかる火の粉をひとつでも払うことが出来れば、それで死んでもいい。
−−マスター!
クラウドは知らないうちに、一心に祈っている。
海面が揺れた。
クラウドが身を乗り出している前で、小さな泡が立ち始める。
泡が大きくなっていくにつれ、影が浮かび上がってきた。
−−マスターだ!
海面が膨れる。そこから現れたのは海よりもずっと煌めく銀色の流れ。
「マスターっ」
クラウドが呼ぶと、セフィロスは視線だけでその無事を伝える。
そして身軽に、ほとんど跳んでいるような気軽さで、小型船へと乗り移ってきた。
その動作から見てもケガなど負っていないのは一目瞭然だが、クラウドはじっと敬愛するマスターを見上げ不安を押さえ込んでいた。ただ用意していたタオルだけを差し出して。
自ら何があったのかを問い質そうとはしないパダワンの健気さは、充分セフィロスにも伝わっていく。
大判のタオルを受け取ると、濡れた身体を拭いながら、セフィロスは微笑んでみせた。少しでもパダワンの心を穏やかにさせる為に。
「モンスターはいなかった」
「そうですか…」
良かった、小さくクラウドは呟く。
決してセフィロスの能力を過小評価しているのではない。
クラウドは純粋に、セフィロスが傷つかずにすんだことを喜んでいるのだ。
「その代わり、おもしろいモノを拾ったぞ」
セフィロスの手が目の前に差し出されてきた。
クラウドが覗き込むと、そこにあったのは小さな青い石だ。
セフィロスの指先ほどの大きさしかない石だが、とても美しく輝いている。
ただの石でないのをクラウドはすぐ察知する。
魔晄の気配のする石。いや、気配というのにはもっと曖昧な、匂いと形容すべきか。
これがきっと目的のモノだったのだ。
「手にとってみろ」
マスターに促されて、クラウドは指先で石を摘む。
その瞬間、石から指先を伝い歌声が聞こえる。紛れもない歓喜の歌だ。
驚きにクラウドの肩が揺れたが、石は放さなかった。
歓喜の歌を歌いながら、石が外観はそのままで、中身がゆっくりと変化していくのを感じる。
そして歓喜の歌が終わる頃に、石の変化も終わった。
−−クラウドの傍へ連れていけ、だと…
あれは、セフィロスのパダワンなのだ。
他の誰でもなく、セフィロスが愛する、大切な少年なのだ。
セフィロスだけの可愛い弟子だ。
例え星の欠片だといえども、己以外に触れさせるつもりなど、毛頭ない。
クラウドをもっとも必要としているのは、セフィロスなのだから。
他に渡すなど有り得ない。
セフィロスが自ら、クラウドを求める者を〜例えそれが人ではない意志だけの存在であろうとも〜傍へと連れていくなど言語道断。
闘気が冷たく、増す。
波にゆうるりと揺らいでいた銀髪が、明確な意図をもって広がっていく。
その意図とは−−殺気だ。
すでに己の一部と化している正宗を、セフィロスは見せつけるようにして構えた。
(あれは、俺のパダワンだ)
セフィロスだけの、たったひとつの。
(お前たちをクラウドに会わせるつもりはない)
むしろ、
(俺がきれいに消し去ってやろう)
光の少ない海底なのに、正宗はセフィロスの殺気を受け、ぎらぎらと輝く。
意識たちも、その殺気に気づく。
(やめて、やめて)
(どうして?)
どうしてだと?
決まっているではないか。
(お前たちが−−クラウドを求めるからだ)
向けられた殺意に、意識たちが慌てふためく。
(求める?)
(求めるですって?)
(どういう意味?)
(何?)
(この人、何を言ってるの?)
(私達はただ)
(そうよ。私達は求めているんじゃないわ)
(あなたと同じ気持ちじゃないの)
(傍にいたいだけ)
(傍にいたいだけ)
ふん、と嘲笑して、
(命乞いか…)
(クラウドの傍にいたいなどと−−)
(許す筈などないだろう)
(傍にいて、クラウドに何を求めるつもりなのだ)
(あれは俺のだ)
(俺の声だけを聞いて、俺だけを見ていれば良い)
(こうるさいお前達など、クラウドの傍に置けるか)
(違うわ)
(違うの)
(あなたは誤解しているわ)
(誤解だと!?)
(私達は、きれいなあの子に何も求めないわ)
(そうよ。何をして欲しいとは思わない)
(私達が願っているのは、そんなんじゃないの)
(聞いて)
(ちゃんと最後まで聞いて)
(私達は、石に戻りたいだけなの)
(石になりたいの)
(ただの塊でいたいの)
(こんな風に考えたりしたくないの)
(こんな風にバラバラに考えたりしたくないの)
(ひとつに戻りたいの)
(眠っているだけの、ひとつの石でいたいの)
(静かに眠っていたいの)
それには、
(私達の力ではどうにもならない)
だから、
(きれいなあの子の傍でなら、それが出来るの)
(あの子はきれい)
(とってもきれい)
クラウドをきれいだと手放しで褒めるのさえ、セフィロスは許せない。
(黙れ!)
(お前達は見るな!)
(見てるんじゃないわ)
(見てるんじゃないわよ)
セフィロスの怒気にも意志たちは退かない。
(心よ)
(魂の形よ)
(きらきら輝いて)
(あなたには見えないの?)
(あの子の魂はあんなにきれい)
(きれい。きれい)
(星に愛されているわ)
(星に愛されているの)
(あの子には星の加護があるの)
だから、
(私達はあの子の傍でならば、ただの石に戻れるの)
(何も言わない)
(何も聞かない)
(眠るだけ)
(眠るだけの、石)
うっとりとした意志が、偽りを言っているようには感じられない。
セフィロスの怒気も引っ込む。
(石に戻ると言うのか?)
(そうよ)
(そうよ、そうよ)
(ただの石になると言うのか?)
(そうよ)
(そうよ、そうよ)
(あの子が星に愛されている証になるの)
(あの子は私達を傍に置くことで、星の加護を強く得られるわ)
(護ってあげる)
(お守りになるわ)
(私達にとっても)
(あの子にとっても)
(あなたにとっても)
(良いことばかり)
(良いことばかり)
(ねえ、お願い)
(私たちをあの子に傍に連れていって)
(お願い)
(お願い)
(お願い)
星の加護−−この言葉にセフィロスは殺気を潜めた。
この意識たちの言葉が本当だとすれば、これだけの魔晄。確かにクラウドに相応しい護符となるだろう。
セフィロスとて解っている。
全力でクラウドを護る覚悟はとうに持ってはいるが、それだけではどうにもならない事の方が多い。
マスターとパダワンだとて、常に傍に居続けるというのでもない。
第一、クラウドは護られるだけの存在であるのを望んではいない。
セフィロスの目の届かない所で無茶をやってのけるのだ。つい先日も己の手首を切り落とそうとしたではないか。
縦長に切り裂かれた、翠の瞳を石に向ける。
(絶対だな−−)
(絶対にクラウドを護ると、誓えるか)
帰ってきた意識は明快だった。
(ええ!)
(誓うわ)
(約束よ)
(私達ただの石となって、きれいなあの子の盾となる)
(強い盾になるわ)
(護ってあげる)
そこに偽りはない。
セフィロスは正宗を収める。
青い小さな石。だがこの石はそれだけではもちろんないのだ。
石の思いもしない変化を目の当たりにしたクラウドは、呆然とするしかない。
「クラウド−−」
呼ばれて顔を上げると、少しばかり心配げなマスターの美麗な顔があった。
「この石は…なんなのですか?」
「お守りだそうだ」
「お守り…?」
「ずっと身につけていればいい」
セフィロスの長い指が、クラウドの耳朶に触れる。
「ピアスにしよう。そうすればずっと身につけていられるからな」
言われて、手の上にある石をまじまじと見つめる。
確かに普通の石ではない。かなりの魔晄の力を有した石なのだろう。そのくらいはクラウドにも解るが…
−−お守りって?
腑に落ちないが、ただこの石が自分に敵意を持っていないのも。むしろクラウドに好意を抱いているのであろうことも、わかる。
それにマスターがお守りにと言ったのだ。
セフィロスがクラウドに害をなすモノを、傍に置かせる訳などない。
「お前の瞳と同じ色をしているな」
セフィロスの大きな手が、青い石ごと、クラウドの手をそっと包む。
同時にセフィロスは長身を屈めて、顔と顔がくっつかんばかりとなる。
見慣れている筈なのだが、やはり完璧すぎるセフィロスの美麗さが急接近してきて、クラウドはぼうっとしてしまう。
低く甘く押さえた声が耳元へと注がれて。
「誕生日おめでとう、クラウド」
柔らかい感触がクラウドの唇にタッチした。
「マイパダワン−−」
それはセフィロスからのキス。
クラウドにとって生まれて初めてとなる、唇へとキスだった。
エメラルドグリーンの抜けるような海の上で、クラウドは敬愛するマスターからの口づけを、敬虔な気持ちで受け止めていた。
二人の目的地である無人島まではまだ距離がある。
だがなにせ休暇は長いのだ。
急ぐ必要などどこにもない

07年8月にクラ誕お祝いの連載をMEMOにて行いました。SWパロのシリーズで甘い甘いお祝いでした。
| << BACK | HOME | NEXT >> |