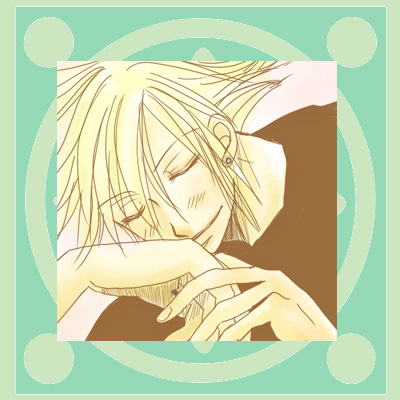
はれくいシリーズ
寂しいとは、どんな音になるのだろうか。
クラウドといると、時折そんな疑問を抱いてしまう。
例えば、不意に会話が止まってしまった時。
例えば、彼が自分に触れてくる直前。果たして、触れても良いのだろうか。それとも触っちゃいけないのか。と、躊躇している時。
ボールを投げようと振りかぶって、突然投げるべき方向を見失ったかのように。クラウドは時折、哀しいのか辛いのか、途方に暮れているのか、定かではない、たぶん全部ごちゃまぜになっているのだろう、そんな表情で止まる。
そんな幼い恋人を目の当たりにすると、いつもセフィロスは感じるのだ。
クラウドは、寂しがっているのだ、と。
そうして、寂しいとは、どんな音になるのだろうか、と。
セフィロスの職業は音楽家。世界的に有名な音楽家であり、最年少でウィーン交響楽団の主席指揮者となった天才である。
セフィロスは今幼い恋人と二人でウィーンに暮らしていた。
寝坊をした二人は、遅いランチをお気に入りの店でとった。
その後焼きたてのフランスパンの匂いにつられて、いくつかを買い込む。
買い物をした袋は大きいのを二つ。一方の手は必ず空けておくのが、二人で外出した時の暗黙の約束事。
なにがあっても、手が繋げるようにと。
感情を出すのが下手なクラウドは、年齢相応の瑞々しい感性をいつも隠している。
隠して、弱味を見せまいと。本当の自分を出すのを恐れていて、いつもぶっきらぼうだ。
だがそのクラウドも今日はご機嫌らしい。いつもは無口なのに、さっきからずっと他愛もないお喋りに興じながら歩いている。
表情もそうだ。セフィロスに劣らないきれいな顔は、ずっと綻んでいた。
太陽は傾いている。赤い夕焼けが恋人を照らしているのを、セフィロスは愛でる。
クラウドの白い頬に夕焼けがあたると、不思議な陰影が生まれた。
夕陽の赤に照らされた青い瞳は、深く深海のような輝きを放っている。形の良い鼻梁の先にある、つんと摘んだような鼻先から、柔らかい唇にかけてのラインは、魅惑的だった。
−−囓りたいな。
囓ったら、極上に違いない。
もっともいつもクラウドの”味”は極上なのだが。
軽く頭を振って、妄想を押しやる。前を向いて歩いていると、ふと違和感を覚え振り返った。
すぐ隣に、クラウドがいない。
更に後方を眺めると、クラウドが突っ立っていた。
顔を横に向けて、石畳にうつる己の影を見つめているではないか。
夕陽にうつる影はいびつに長い。
実際のクラウドの倍はあるであろう影は、石畳の上に下半身部分を、民家の壁に上半身部分をうつす。
石畳にうつっている下半身だけが、やたらと長くて細い。棒っきれのような影の足はバランスが悪すぎる。
それは壁にうつっている上半身も同じ。上半身はやたらと太短い。滑稽というよりは気持ち悪いほどのバランスの悪さ。
セフィロスはゆっくりと突っ立ったままの恋人へと近づいた。
クラウドはなんの表情もうつしていない。魅入られたように自分の影を見つめているだけ。
−−寂しいとは、どんな音なのだろうか?
絶対音感を有する天才にも解けぬ、これは神秘の難問。
この表情を消すのには、どうすれば良いのだろうか?
愛しい少年の寂しさを、どうすれば拭えるのだろうか?
セフィロスの仕事中は、なるべく近寄らないようにしている。
もっともセフィロスは全てを忘れて仕事に没頭するタイプではない。
むしろクラウドから見ると、淡々と仕事をこなしているように思える。
セフィロスが熱くて激しいのは、−−セックス。
睦み合っている時は、クラウドがはちきれそうになる程の情熱を注ぎ込んでくれるが。
それがここ数日のセフィロスはヘンだった。
淡々とこなしている仕事に、今回だけは激しい情熱を傾けているようで、尚更クラウドは仕事場に近寄れなくなってしまう。
幼い頃より天才ぶりを開花させてきたセフィロスにとって、音楽とは切っても切り離せないものだ、とは頭では理解しているが、自分だけに与えてくれていた執着を傾けてるなんて、やはり、面白くない。素直に認めたくはないけど。
素直に認められないもどかしさと、そんな心の狭い自分を嫌悪して、クラウドの機嫌は急降下中。低空飛行をかろうじて保っている状態だった。
今朝も早くからセフィロスは仕事部屋へと閉じこもってしまう。
いつもは五月蠅く聞いてくるクラウドの予定についてもそっちのけで、朝食もそこそこに。
なんだか悔しくて、いつもよりたくさん食べ過ぎた。
重くなった胃を抱えつつ、仕事部屋の扉に耳を当てる。
しっかりと防音してある部屋からは、どんな些細な物音もしない。
そのうちに我に返った。
−−オレ…バカみたい。
聞こえないと解っているのに。扉に、耳なんかあてて。まるでこそ泥みたいに。
ただでさえ低空飛行だった少年は、激しい自己嫌悪に陥る。
−−頭、冷やしてこよう。
上着も持たずに部屋から出ていった。
古い街並みに敷き詰められている石畳は、所々変形している。
地盤かなにかが少しずつズレているのだろう場所や、すっかりと表面が丸くなった所。道がヘコんでいる所もある。
−−あれは轍の跡だ。
クラウドにそう教えてくれたのは、セフィロスだ。
車のタイヤでヘコんでいるのと轍のそれとは、かなり趣がちがう。
車のは削り取った感じだ。無惨な生傷のように思えた。それに対して轍の跡はもっと自然だ。石が自然と風化していくのとよく似ていて、違和感無く位置畳みの一部分と化していた。
跪いて、轍の跡に手を置いてみる。思いの外滑らかな感触をなぞっていくと、己の影にまで届いた。
自分の影−−いびつな影は隠している自分の半身を映す。
影はこう訴えていた−−寂しい、と。
−−寂しい、…か…
本当にいつから自分はこんなに幼くなったのか。
四六時中、自分だけを見て欲しいだなんて。
自分以外に関心を移して欲しくない。
ずっと愛していて、愛してもらっているんだと、実感させて欲しいだなんて。
まるで底の抜けたバケツだ。セフィロスは充分クラウドを愛してくれているというのに。
彼は自分と暮らすことで、多くのモノを犠牲にしているだろうに。
与えられてばかりいる自分は、その事実を解っていながらも、満足出来ないでいる。
まるで赤ん坊のように、泣きわめいているみたいだ。
−−こんなんじゃダメだ。
セフィロスはきっと呆れる。
才能溢れる彼には、自分以上に相応しい相手など、掃いて捨てるほど近寄ってくるのだ。
今はどんなわがままも笑って許してくれるだろうが、いつかきっと−−終わりが来る。
その時自分はどうなるのだろうか。
柔らかに轍の跡はひんやりとして心地よい。
長い長い年月をかけて、相容れない筈の石畳と轍はひとつに重なっている。
−−この轍みたいに…
−−こんな風にセフィロスに心に跡を残せるようになりたい。
なるべく柔らかく。
出来るだけ自然に。
セフィロスに一部となって残ることが出来れば良いのに。
いつの間にか日が傾き始めている。
誰かに呼ばれたような気がして、クラウドは立ちあがった。
辺りを見回していると、銀色の光が見える。
−−セフィロス!?
大股で走るセフィロスは、あっという間にクラウドの傍までやってきた。
「散歩だったのか、クラウド」
一声かけてくれれば、一緒に出かけたのに。と続けてくるセフィロスの顔をまともに見られない。
じっと足下の轍跡へと視線を注ぐだけ。
こんなクラウドの様子をどう思ったのか。セフィロスは少年の所在なさそうな手を握りしめる。
大きな手だ。指がとても長くて美しい。
この手と指ならば、どんな楽器でも使いこなせるだろうし、どんな複雑な曲でも演奏出来るだろう。
こんな部分でさえも、こんなにクラウドとは違いすぎる。
「さあ、家に帰ろう」
幼子のように手を引かれたら、もう逆らえない。
大きく美しい掌に包まれて、引かれて家路へと向かうのは、たまらない幸福だ。
この幸福が失われたとすれば、どうなるのだろうか?
この幸福を忘れられるのだろうか。
俯いたクラウドの顔が強張ってしまう。それは”寂しい”表情。
セフィロスは注意深く、クラウドを見つめていた。
クラウドの表情に彼は握る手の力を込める。
戸惑いながらも、それでもセフィロスに応えるように、掌の中の小さな手に力がこもった。
二人で暮らしている家に戻ると、セフィロスは自ら仕事部屋へと恋人を招き入れた。
一口に仕事部屋と言っても、セフィロスのは複数ある。
この高級マンションの最上階フロアーは、全てセフィロスのモノなのだから、スペースには事欠かない。
どれもしっかりとした防音がなされているのは当然だが、部屋の趣と用途は様々に違う。
自宅でミキシングまで出来るレコードスタジオのような部屋。ここが一番広い。
ピアノが置いてある部屋。ここは主に作曲やアレンジの創作に使われているようだ。
曲を聴く専用の部屋もある。この部屋にはクラウドもよく入っていた。
セフィロスが案内したのは、ピアノのある部屋だ。
この部屋はセフィロスの仕事部屋の中で一番狭いが、一番安易に立ち入れられない部屋でもあった。
なにせ、セフィロスの創作の現場。インスピレーションが天啓の如くに舞い降りてくる神聖な場所なのだ。
ピアノはスタンウェイ。力の技巧も充分すぎる天才セフィロスが扱うに相応しい名器。
セフィロスは部屋に置いてあるソファにクラウドを誘う。
クラウドをソファへと座らせてから、彼は自ら跪いた。
長身だから跪いてもやはり迫力がある。ソファに座ってしまったクラウドよりも高い位置に美麗な顔があった。
彼はまだ握っているクラウドの手を大切そうに掲げる。
「曲を作った」
「聞いてくれ」
この言葉に、クラウドは己の手を引いてしまう。もっともセフィロスはそれを許さなかったが。
「オレ…音楽なんてわからないから……」
批評なんてとても出来ない。ましてや天才セフィロスの批評など。
「クラウド−−」
「お前の為に作った曲なんだ」
「お前に聞いて貰わなければ、意味などない」
「オレの!?」
−−なんで?
疑問を露わにするクラウドに、セフィロスは苦笑で応じる。
「俺は音楽家だから、恋人に音楽を捧げるのは当然だろう」
「まずは、聞いてみてくれ」
−−それだけで、良いから。
握ったままのセフィロスの長い指が、そっとクラウドの手の甲を撫でていく。
手はそのまま離れて、セフィロスはピアノへの向かった。
そして、演奏が始まる。
最初はひとつの和音から。
澄み切ったシンプルな調べだが、どこかもの悲しい気がする。
曲調はむしろ淡々と。だが不思議と耳に残るのだ。
−−なんだろう、この感じ…
クラウドの考える音楽とは、明暗や喜怒哀楽などはっきりとしたメッセージを情熱的に語るものであるが、この曲は違う。
重い訳ではないが、軽いのでもない。
明と暗が入り交じっている。だからこんなにもの悲しいのだろうか。
そのうちにまた別の音が入ってきた。
主旋律を包み込むようにして、ゆったりとたゆとう。
音楽というよりは、水の流れのようだ。
水の流れの中、クラウドはゆっくりと漂っている。その流れはあくまでも心地よく、目を閉じると自分という自我が身体という器を超えて、流れと同化していくような気さえする。
クラウドはセフィロスの声を聞いた。
主旋律はクラウドだ。
喜怒哀楽明暗の入り交じったカオス、それがクラウド。
入ってきた別の音こそがセフィロス。
主旋律を変えようとはせずに、ただ包み込んでいる。
セフィロスはどんなクラウドも否定しようとはしていない。
ただどのようなクラウドであろうとも、共に流れていこうと。
曲の善し悪しは分からないが、クラウドは願う。
これからもずっと、セフィロスという流れにたゆたっていたい、と。
そうして曲は終わった。
「お前は不意に遠くへ行ってしまう」
「何を考えているのか、俺には解らない存在になってしまう」
ピアノに向かい合っていても、いつもクラウドのことを考えていた。
そのうちに遠くに行っているクラウドを見て”寂しい”と感じるのは、単純にクラウドが寂しい顔をしているからだけではなくて、恋人を理解出来ないと感じる自分も同様に寂しいのだと知った。
−−寂しいというのは、どんな音になるのだろう…
そこで主旋律が生まれる。
寂しいというのは、様々な側面がある。複雑に入り交じった果てにある感情を、人は寂しいと表現するのだ。
「俺は決めたんだ」
「お前が何を感じ、どんなことを考えていようとも、お前と共に生きていこうと」
クラウドを柔軟に包めるだけの、大きな流れとなろう。
これが、セフィロスの決意。
「言葉を嫌うのならば、何も話さなくていい」
だから、
「ずっと傍にいられる優越を、俺にくれ」
−−コイツ、やっぱりバカだ。
傍にいたいのは、こっちだっていうのに。
でも、話さなくていいと言ってくれたのだから、絶対にクラウドからは言わない。
「あんた…バカだよな……」
ソファから立ちあがったクラウドは、ピアノの前にいるセフィロスに跪く。
鍵盤の上にまだある、美しい指をそっととって、口づける。
永遠の敬意をこめて。
END
| << BACK | HOME | NEXT >> |