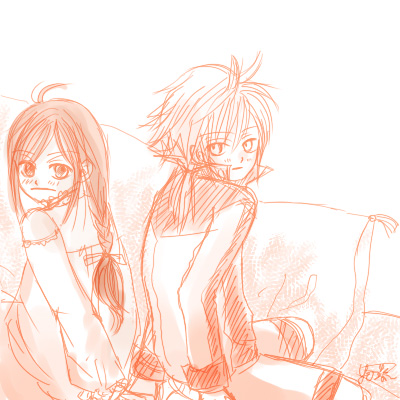金銀の寄り道で思いつきました。
ある意味吸血鬼ネタだけど、金銀とは関係ない世界観です。
全体的にエログロ。
後半は特にその傾向が強くなります。
今回は前半だけで説明文みたいなもの。
セフィクラ。ショタ警戒警報、特に後半発令。
スルースキルをあげて、さあどうぞ。
※※※
永遠の忠誠を誓うセトラの女王、エアリスの帰還の知らせにセフィロスは動きを止める。
鍛錬に振るっていた愛刀を、滑るように鞘へと戻すと、無言のまま女王の元へと向かう。
セフィロスはソルジャーだ。しかも1st、2nd、3rdとランクづけされているソルジャーのトップ。
永遠にセトラへと仕えるべき存在であるセフィロスだが、彼は女王の騎士であるロマンチシズムとは無縁の男であった。
月光のような銀髪に縦に裂けた翠の瞳。美麗すぎる容貌を支えるのは、一際高い長身にしなやかで逞しい戦士の身体。
彼はセトラを護るためのソルジャーなのだ。
セトラとはこの星に生きる最も古い種族である。
星の声を聞き自然を愛して、この星を豊かにしてきたのはセトラだ。
そういう意味ではセトラはこの星の守り手であり、光の存在であるともいえよう。
だが強い光は強い闇を産む。反剋。ネガとポジ。
光と闇は反するものにも思えるが、その実背中合わせに立っているだけのひとつなのだ。
セトラとは闇の存在でもあったのだ。
いわく――糧。
セトラは普通の食事を摂らない。
セトラのエネルギーは精気〜エナジー〜である。
自分たちが育てた花や木々、そして人からセトラはエナジーを吸って己の糧とするのだ。
エナジーとは生物の体内に循環するライフストリームである。
手や唇で触れただけでもエナジーは摂取出来るが、セトラが好む濃厚なエナジーは精液と血液からであった。
またセトラは非常に長命である。エナジーを糧としているからなのか、そもそも寿命というものがないのだ。
マテリアを扱い魔法もよく出来、病からも老いからも無縁のセトラであったが、だからと言って敵がないのでもない。死とも無縁ではない。
まずセトラはモンスターから狙われていた。食物としてのセトラが人や動物よりも美味であるのもあろうが、星の正規の循環から外れたいびつな存在であるモンスターにとって、星のライフストリームを正常にさせるセトラはやはり敵なのだろう。
モンスターはセトラを選んで襲い、髪の一筋までも好んで喰らった。
だがモンスターと敵対しているものは、この星のほとんど全てである。セトラにとってモンスターは驚異ではない。
魔法により身を守る術を心得ているセトラが、モンスターに喰われることはほとんどないのだ。
それよりも遙かに驚異の敵は残念かな一部の人間であった。
セトラの卓越した能力を前に、人間の反応は大きくふたつに分かれる。
敬意をもつ者と悪意とする者だ。
前者はセトラを崇めた奉ってきた。神と同じだけの神聖な存在であると考えたのだ。
それに比べ後者は惨いものである。彼らはまずセトラの能力をねたみ羨んだ。
そうしてどうにかしてセトラの能力を我が物にできないかと考えたのである。
セトラの能力はあくまでも血統の成せる業。そうだと解っていても人は諦めなかった。
彼らは集団となりセトラを狩る。偽りの優しさでセトラをおびき寄せ、捕らえると様々な実験を施したのだ。
ある者は不老不死を求め。ある者は魔法を求める。
だがそのどちらも帰結するところは、セトラの虐殺でしかなかった。
セトラがエナジーを糧とすると解っていたからなのか、セトラの能力が普通の方法ではどうやっても我が物にならないと悟ると、人はセトラの生き血を飲み干し肉を喰ったのだ。
まるでモンスターのように。
長寿ということは生殖能力が低いということ。元々個体数の少なかったセトラだったが、長い間人に狩られてしまい、種族としてはほぼ滅亡状態となる。
星はこの事態を深く憂いた。
星にはセトラが必要だったのだ。セトラだけが星の声を聞き、星を正常に機能させることが出来る唯一。
星はセトラを護るべくジェノバと呼ばれている、全く異質の生命体を呼んだ。
そしてジェノバと星は交わり、ソルジャーを生み出す。
セトラの為だけの最強の戦士。セトラの血統だけに忠誠を誓う不滅の騎士を。
ソルジャーの出現によって、セトラは絶滅の危機から救われる。
だがこの星に散らばるセトラの個体数はまだまだ少ない。
現在セトラを納めているのはエアリスという。セトラの証ともなる栗色の髪と緑の瞳を持つ少女だ。
もっとも少女なのはあくまでも外見だけのこと。
人の年齢で当てはめたとするならば、エアリスはすでに人の数世代分は有に生きている。
ある時エアリスはこう言ったのだ。
――セトラ、見つけた。
と。
エアリスは優秀な魔導師だ。特に白魔法はセトラ随一である。
だがそうだと解っていても、セフィロスはエアリスの言葉をまず疑った。
セトラの血統は太古から管理されている。セトラの能力はセトラの血統しか出ないため、セトラと他の種族〜人間だが〜の血が交わらないようにされてきたのだ。
ソルジャーにとってセトラの護衛と共に、血統の管理も重要な使命のひとつ。
よってソルジャートップであるセフィロスは、セトラの血統については全て知り尽くしている筈なのに…
――でも、いたの。
――わかるの。
エアリスはこの意見を曲げなかった。
挙げ句の果てにソルジャーの供を一人だけ連れて、そのセトラを迎えに出ていってしまったのだ。
そして、今日、この忘らるる都にやっと戻ってきたと言う。
エアリスが呼びつけてきたのは公式の間ではなく、客間であった。
エアリスの私室にも近いその客間は、外交上の賓客だけではなく本当に近しい者を泊める場所である。
このことからも連れて帰ってきたというセトラにエアリスがどれほど大きな期待をかけているのがわかるというもの。
エアリスがセトラだと認めているのだから、連れ帰ってきた者がセトラなのは間違いない。
だがだからこそセフィロスはその者について詳しく知らねばならない。
セフィロスが静かにノックすると、応答はすぐにあった。
「どうぞ」
エアリスだ。
重々しいドアを開けるとまずこの客間のリビングが広がっている。
この星の自然をこよなく愛するセトラの住む場所は、どこも共通点があった。それは自然物をふんだんに取り込んで、加工の手をあまり加えないことだ。
この客間もそうだった。
太古は海であった忘らるる都のエアリスが住むこの城は、海の生物が結晶化した貝の形をしている。
内部も鉄やコンクリートではなく、驚くほど丈夫で耐久性と魔法防御に優れた海の生物の化石で出来ていた。
部屋の窓枠から滑るように張り出している部分が、そのままリビングのテーブルとなっている。カーテンなどの布類も色調を合わせた淡く白く青い海の色。
どこまでも淡い海の世界の中で、女王エアリスは立っていた。
セトラという種は元来素朴で純真だ。それは容姿にも現れている。
エアリスは年若い娘の姿をしている。女王として身に付いた気品と威厳は滲むものの、外見だけしてみればただの可愛らしい娘としか映らないだろう。
単純な美醜だけで計るならば、セフィロスの方がエアリスよりも遙かに美しい。
それでもやはりエアリスはセトラの女王だ。セトラに忠誠を誓うという本能が、セフィロスを惹き付けてやまない。精神的なものだけではなく、肉体的にも、だ。
星はソルジャーを創造する際、セトラとソルジャーが運命を共にするべく、ある仕掛けを施した。これによってどれだけ狩られようが、人との接触をしてしまうセトラの弱味を克服したと言えよう。
すなわちセトラの糧の問題である。
セトラはエナジーを糧とする。生物からでもエナジーは搾取出来るが、もっとも好む濃厚なエナジーは精液と血液。それは人の精液と血液なのだ。
セトラは美味なる糧を入手するべく、人と肉体的な交わりを持つ。
セックスの最中にセトラは人に牙を立てるのだ。セトラにエナジーを搾取されるのは、すさまじい快感を人にもたらす。それはどのようなセックスでも到達できない、精神と肉体が感じられる最高の極致なのだ。
陶酔の最高潮に押しやられ、人は血液だけではなく精液をセトラに捧げる。
人とは快楽に弱い。セトラ狩りが広まったのも、このセトラでしか為し得ない最高の極致を欲したのも一因であろう。
またセトラも狩られると解っていながらも、糧を求め人と交わることになる。
どれだけ強い魔力を有していようが、セックスの際にはセトラとて無防備となってしまう。ここを人に狩られてきたのだ。
星はセトラの糧となる運命をソルジャーに与えたのだ。ソルジャーの精液と血液はセトラにとってのごちそう。
またセトラという種自体が、ソルジャーにとっての媚薬とした。
よってセトラは数多くのソルジャーと交わり、糧を得る。
ソルジャーも求められれば歓んでセトラと交わってきた。
需要と供給の関係はあくまでも情が介在しないシビアなもので、多くのセトラは特定のソルジャーを指定せずに、食事を日替わりに楽しむように数多くのソルジャーと交わっている。
セトラにとってソルジャーとは、あくまでも下僕なのだ。
同様にソルジャーにとってもセトラとは、仕えるべく主でしかなく、特定の誰に忠誠を誓うのではなく、セトラという種自体に仕えてきた。
特にセトラの数が減ってしまってからは、セトラはソルジャー皆の共有財産であるのだが――例外とはどこにでもあること。
セフィロスは例外の片割れである女王へと頭を垂れる。
セフィロスの苦々しい心中など見通しているエアリスは、殊更純真そうな笑顔を作って応じた。
「ただいま、セフィロス」
「ご無事のお戻り、なによりです」
セフィロスのフラットすぎる態度に、エアリスは心中舌を出す。
――きっと驚くヨ。
この鉄面皮なセフィロスが、どれほど驚喜するか。
想像するだけでエアリスは楽しくてたまらない。
「エアリス様。セトラを連れ帰ってきたと聞きましたが」
「うん。そうだヨ」
「わたしの血を与えたから、今は眠ったままなの」
「エアリス様の血をお与えになったのですか」
うん。
「だってあの子、ずっと人間として育てられてきたんだもの」
セトラを敬虔に信仰している山奥の小さな村に隠されていた少年。
彼はセトラの血統を強く引きながらも、人として生きていたのだ。
セトラ狩りを知った周囲から、人として育てられることで護られてきたのだ。
少年は自分がセトラであることは知らずにいた。
そこにエアリスが現れたのだ。少年を護ることに不安を抱えていた村人は、エアリスの登場に安堵し、女王に少年を託す。
だがセトラであることすら自覚のなかった少年には、この状況の変化についていけない。
そこでまずエアリスは、もっとも濃い己の血を少年に与えたのだ。セトラとしての覚醒を促すべく。
血を与えた時、エアリスは見た。
「あの子、わたしと同じ」
セフィロスが翠の目を細める。
「わたしと同じ、ハーフセトラだヨ」
セトラと人が恋に落ちることは、ままある。
エアリスもそうだった。母イファルナは人である父ガストと恋に落ちる。
セトラと人の混血は生まれないとされているのだが、その実稀に、天文学的な確率、つまり奇跡の確率で出来ることがあるのだ。
エアリスもそうであった。出来ないとされていたガストの子供をイファルナは身籠もる。
そしてエアリスが生まれた。
セトラと人との混血は素晴らしく高い能力を有している。
エアリスは生まれながらに強い魔力を持ち、セトラの女王となったのだ。
セフィロスもむろんこの事実を知っている。
「――それでは…お連れになったセトラも…」
「わたしと同じか、もっと強い力を持っているのヨ」
「しかも、あの子、男の子だしネ」
「男…――」
セフィロスの鉄面皮が崩れる。
セトラはどうしてだか、男に恵まれない種なのだ。男と女の比率がアンバランスで、女200に対して男1。ただでさえ子供に恵まれないというのに、これではどうしようもない。
セトラの種が衰退する大きな内因であったのだ。
「男の…ハーフセトラが――」
「すごいでしょ」
「…はい」
セフィロスは未だ夢がさめやらぬ面もちだ。こんな顔のセフィロスを、エアリスは初めてみる。
――あの子を見たら、セフィロスもっと驚くヨ。
「寝室で眠ってるから、見に行けば」
「良いのでしょうか」
「ザックスが側にいるから、彼と交代してくれれば助かるヨ」
ザックスはエアリスだけのソルジャーなのだから、出来れば他のセトラの側には置きたくはない。
「わかりました。では失礼いたします」
「あの子、目覚めたら教えてね」
「はい」
長い足を早く動かして、セフィロスはあっという間に寝室に向かっていった。
突進、とも言えるその行動に、エアリスはついに笑いが堪えきれなくなってしまったのだ。
寝室には天蓋のついた大きなベッドがひとつだけある。
このベッドも天蓋も、すべて淡く白く青い海の色だ。
セフィロスが入室すると、天蓋の内側から一人のソルジャーが出てきた。
ソルジャーザックス。女王エアリスの例外。
彼はソルジャーでありながら、エアリスとしか交わらない。またエアリスもザックスの血しか吸わない。
セトラとソルジャーでありながら、彼らは恋仲。例外なのだ。
セフィロスに上背こそ劣るが、逞しさは遜色ない。実力もかなりのもので、魔法を使わない戦闘だけならば、セフィロスをもしのぐ。
「よお」
気安い態度のザックスなど今のセフィロスの眼中にはなかった。
「お姫様はまだお休みだぜ」
「姫様…?」
「男だと聞いたが…」
「そーそー。確かに男の子だな」
でもな、
「エアリスよりもずっとお姫様みたいなんだよなあ」
ま、見てみろって。
ザックスは天蓋をめくると、セフィロスをベッドの側へと導いた。
大きなベッドの中央で、すやすやと眠っているその姿を認めて、セフィロスは衝撃に打たれる。
――これは!?
透き通る白い肌。血管や骨でさえ透けてしまいそうだ。
ふっくらしたバラ色の頬に、花弁のような淡い唇。眠っているというのにその繊細な容貌は疑いようのない美であった。
産毛の一本一本までもがかぐわしい。
セトラはこんな隅々まで、こんなにきれいに出来てはいないのに。
男でもなく、女でもない。名前を付けることさえ出来ない。そんなとても特別な何かに思えた。
ただ大きな目にびっしりと生えている長いまつげも、作り物のようにととのった眉も、なによりも髪も、どれもセトラにはあり得ない色、金だったのだ。
セフィロスは無意識のうちに身を乗り出してしまう。
そんなセフィロスの行動などザックスにとっては当然であった。
セフィロスの驚愕はザックスの驚愕でもある。ザックスとて初めてこの少年を目にした時、驚きで死ぬかと思うほどの衝撃を受けたのだから。
少年の外見はセトラとは似てもにつかずに、きれいだ。
それなのに彼は確かにセトラなのだ。ソルジャーが永遠の忠誠を誓っている媚薬、セトラを間違える筈などない。
だがそれでもしばらくは信じられなかったのだから。
「目の色もスッゲーぜ」
ザックスは一拍おいて、
「緑じゃねえ。――青だ」
「青みがかった緑じゃねえ。緑がかった青でもない。本物の、濁りのない青だった」
それはそれは美しい、青。
「そのような…セトラなのに」
信じられないとセフィロスは力無く首を振る。
「ハーフセトラだからか知らねえが、この子は特別だな」
すやすやと眠る少年。年の頃は10代半ばだろうか。もっともセトラだ。外見と実年齢がイコールであるとは言えないが。
「エアリスに血を与えられたからすぐに眠ちまったから、俺もあんまり動いてるとこ見てねえが――」
ザックスはこの男にしては珍しくこっそりと、
「怯えてる様子なんか、めちゃくちゃ可愛かったゼ」
エアリスに血を与えられた瞬間の少年の様子は、舐め回したいくらい壮絶に愛らしかった。びくびくと震えすっかりと怯えて、それでも最後はセトラの本能によって、血を吸ってしまう。エアリスの例外であるザックスでさえ、惑わされそうになったくらい、この子は強烈な媚薬である。
「ザックス、――お前…」
「これ、エアリスには内緒な」
ザックスはそう言うと、少年の額に掛かった金髪を指先で払う。
セフィロスはそんなザックスの行動に強い不快感を覚えた。手でむんずとザックスの手首を捕まえると、彼が文句を言うよりも先に、
「気安く触れるな」
「なんで?セトラはソルジャーみんなの大切な主だろ」
確かにザックスの意見は正しいのだが、この少年に限りセフィロスはその理屈を認めることなど出来ない。
「触るな。お前はエアリスでも好きなだけ触っていろ」
「ええー!触るくらいいいだろ」
「なにもセックスするって言ってるんじゃないんだし」
「それでも駄目だ。この子は俺が面倒をみる」
「おいおい!それは聞き捨てならねえな」
ザックスが言葉を続けようとしたその時、不意に寝室を流れている風が変わる。
ソルジャー二人はぴたりと言い合いを止めると、眼差しをベッドへと向けた。
少年の薄い瞼が揺れる。
そしてゆっくりと目が開いていく。
ザックスの言う以上に美しい、それは生まれたての青であった。
※※※
あんまり長くしないように、次くらいでおしまいです。
|