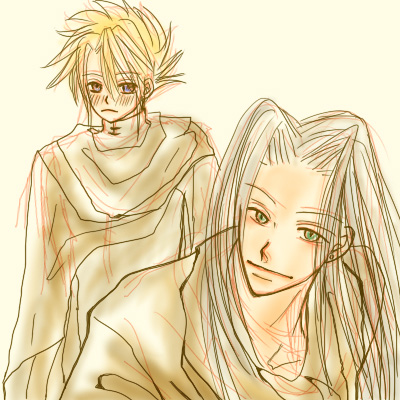こんにちは、びーこです。
Y子さんからのサイト運営に関するお知らせをまだ読んでいらっしゃらない方は、
ひとつ前↓の記事に目を通してくださいませ。
よろしくお願いします。
では少し間が空きましたが、前回の続きです。
※※※
たった一瞬の邂逅で、そこまで理解してしまった英雄の存在を、クラウドは意識的に閉め出すのに必死だった。
もう二度と会わないと。
もし会ってしまえば――自分はこのままでいられなくなる。
心地よく何の変哲もない村での日常から、離れなければならなくなる。
そう、あの優しい母からも離れなければならない。
それなのに、
――あの男!何を考えているんだ。
ごあああああ。
その時天空にいる竜王が、天地を揺るがせる咆吼をあげた。
びりびりと大気が振動する。大気だけではない。立っている地面からも響いてくる。
クラウドもリーダーも、クラウドに襟首を捕まれている兵も、一斉に空を仰ぎ全身を強張らせる。
「まさか…召還獣を呼び出すだなんて!?」
兵の叫びはもっともだ。
普通ならば召還獣を、しかもバハムートなどをこんな場所に呼び出したりはしない。
だがクラウドは常識として兵の言いたいことも解る一方で、召還獣まで呼び出したセフィロスの行動も理解していた。
何せ彼は完全なるスタンドアローンなのだ。
何物も必要とはせずに、何物からも本当の意味で必要とはされていない。
そんな彼に常識など関係あるまい。
竜王は咆吼の余韻の中、上空から見下ろしている。クラウドだけを。
――やはり、目的はオレか。
クラウドは竦んだままのリーダーへと向き直る。
片手で兵の襟首を締め上げたままだが、自分よりも遙かに体格の良い男を、華奢な少年が片手だけで振り回している異常さも、竜王出現に比べれば大したものではないようで、リーダーも兵自身も気づいていなかった。
「おい。この男を連れて早く山を下りろ」
クラウドの一言によりハッと我に返ったリーダーは、きょとんとした顔つきで、
「……クラウド?」
「いいから。早く行け」
「それは……クラウド、ダメだ」
それでも頑なにクラウドを気遣ってくれているリーダーを見て、クラウドは少しだけ余裕が生まれた。
「あの竜王の目的はどうやらオレらしい」
「だから、早くここから離れてくれ」
「クラウド!目的がお前だっていうのなら、なおさら――」
リーダーを遮って、
「いいや。だからこそ、オレ一人にしてくれ」
固い決意を含んだ言葉に、それ以上は何も言えなかった。
「必ず、――村に帰ってこいよ」
「…ありがとう」
不器用な少年の、それでも応じてくれるはにかんだ答えに、リーダーはこんな時なのに穏やかな気持ちになった。
こうと決まれば素早く動かなければならない。
リーダーは兵の背中を荒っぽく叩く。
「逃げるぞ」
「いや…、でも……」
バハムートを前にして、少年一人きり残しておくというのか。
狼狽する兵に、
「あいつは大丈夫だ」
それよりも、
「クラウドの足手まといにならないうちに行くぞ」
もう後ろは振り向かなかった。兵を乱暴に促しながら、リーダーはニブル山を下っていったのだ。
残ったのはバハムートを見上げるクラウドと、クラウドを見下ろすバハムートと。
そして、
「いつまでそこで隠れているつもりだ」
ミニマムで隠し持っていた剣を取り出しながら、クラウドは上空の竜王ではなく、違う方向へと厳しい視線を向ける。
「――わかっていたのか」
クラウドのよりも太く低く、どこか愉しんでいるような声が応じた。
「当たり前だろう」
「気配も隠さずに、ずっと見ていたくせに」
――悪趣味。
神羅の英雄にも容赦なく、クラウドは鋭く睨む。
冬枯れしている木々の間から、銀色のシルエットが現れた。
銀髪に黒革のコート。どちらもセフィロスでなければ長いシルエットがサマにならず、相当みっともなくなっていただろう。
彼のずば抜けた長身と、見事な黄金率の体躯だからこそのこの完璧さだ。
セフィロスという男は、自分の美麗なる容姿がどれだけ他者に大きく作用するのか、考えたことがあるのだろうか。
自分の美しさを計算しているのかと思わせる優雅さで、長い足を使いむしろゆったりと近づいてきた。
歩く度に銀髪が揺れ、セフィロスの神秘的な美しさを増大させる。
絶世の美しさ故の感嘆と、威厳あるプレッシャーを同時に感じさせる男。
こんな男は、英雄という称号を除いても、他には存在し得ないであろう。
長身が歩いてくる姿は、ゆっくりと優雅に見えた。なのに動作は速い。
神秘的な翠の瞳を意識するよりも先に、セフィロスはすでにクラウドのすぐ前に立っていた。
長身を畳み込むようにして、革手袋をはめたままの長い指先で、尖ったクラウドの顎を掬う。
とっさに無礼な手を払おうとしたが、あまりにもその手つきが優しすぎて、それが意外で、クラウドの動きは止まってしまった。
ハッと思う間もなく、鼻先を擦れあわせんばかりの至近距離に、端正で美麗な顔がある。
これだけ近距離なのに、どこにも足らないところがない。
完璧な美貌は非の打ち所が鳴く硬質すぎて、生きているという精気が感じられないのに、ただ一点だけその双眸だけがセフィロスという男の確固たる意志を写し取っているようだ。
こうして見ると彼はとても珍しい瞳をしている。
色ではない。その形だ。
セフィロスの瞳孔はきれいに縦に裂けていた。
こんな瞳孔、ファティマでもあり得ない。
禍々しいほどに神秘的だ。確かに美しい。だがこの美しさは賞賛される類のものでもなければ、どのような豊楽をも含んではいない。
クラウドはそこに絶対的な深淵を認める。
彼は本当に独りなのだ。彼はたった独りで成り立っている。そしてこれからも――
騎士を前にしたファティマの、本能としての献身ではなく、もっと別な何かがクラウドをセフィロスへと突き動かそうとする。
殊更、特別な何かは必要ない。いつも彼の側にいて、声を聞いて、名を呼んで、呼ばれて応じるだけでも、彼はきっとクラウドによって少なくともこの孤独という深淵からは救い出せるのだろう。
小さく尖った顎を愛撫するかのように、手袋に包まれたセフィロスの手が動く。
「外見はずいぶんと可愛らしく出来ているのに――」
「まるでファティマではないような鋭い目つきだな」
ファティマ――この言葉にクラウドは過敏に反応してしまう。
セフィロスから距離をとろうと、身体が勝手に動く。首を振り顎に手を掛けたままの大きな手から逃れようと抗った。
だがそのような反射的な動きは、英雄と呼ばれる騎士にとってなんというものではない。
「動くな」
「お前の目が見たい」
かえってより一層顔が近くなる。
「青だな」
「アイカバーの色ではない、本当の瞳の色だ」
セフィロスの値踏みは瞳の色だけには止まらない。
「遠目でみるともっと小柄なようにうつるが、しっかりと鍛えられている体をしている」
「細い眉。形の良い鼻。そして混じりけのない金髪」
「ファティマは男性形も女性形も皆美しいものだが――」
「お前のは少し違っている」
男でもなく、女でもなく。また人でもファティマでもない。
「確かにお前はただのファティマなどではないな」
「俺の所有すべきファティマとは、こういうモノだったのか」
こうして観察してみて、セフィロスはクラウドがガスト博士の作品であると確信した。
彼はやはり、ガスト博士がセフィロスの為に用意してくれた、パートナーなのだ。
くくく、セフィロスは口だけで笑う。他の者がすれば下卑た嗤いになるだろうが、セフィロスがすれば驚くほどにノーブルだ。振動が直に伝わってきて、クラウドにやっと現実が追いついてきた。
顎に手を掛けられたまま、鋭く睨む。
「…あんた……どういうつもりなんだ」
「どういうつもり、とは?」
「ふざけんなっ!」
セフィロスは明らかにクラウドとのやりとりを愉しんでいる。
自分に向けられているクラウドの怒りさえも、だ。
「どういう理由で何のために、バハムートなんて召還したのかって聞いてんだよ」
「お前を試すために決まっているだろう」
「試す――?」
――そうだ。
「見かけは合格だ」
「俺は触るだけで折れそうな貧弱なファティマなど必要ないからな」
「“ハイ。マスター”しか言えんような人形もいらん」
「お前はちょうど良い」
「見た目よりも頑丈に出来ているようだ」
――心も、身体も。
「ガスト博士は俺に約束をした」
「お前に相応しいファティマを造ってやろうと」
「こうも言っていた」
「ただしそのファティマは俺に選ばれるのではなく――」
「ファティマこそが、俺を選ぶのだと」
「だから試す」
「お前が俺を選ぶのに相応しいかどうか」
至近距離のまま、クラウドの青い瞳に教え込むように囁く。
「クラウド。バハムートを倒してみせろ」
「もしお前がこの竜王を倒せたのならば、俺はお前を認める」
「お前にパートナーたる騎士として選ばれるように、土下座もしてみせよう」
縦に裂けた瞳孔が、鋭く尖っていた。
※※※
英雄殿…ちょっと変態か
|