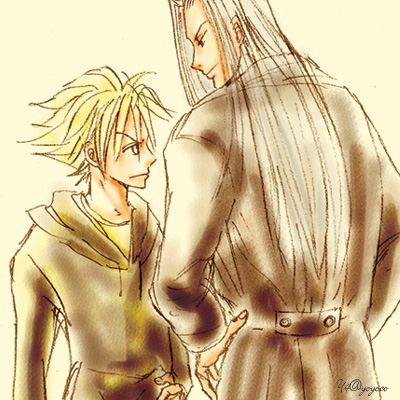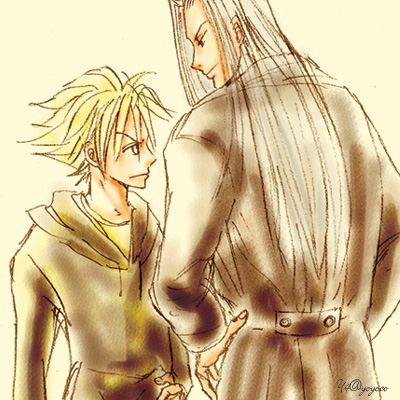拍手LOG
神羅の寮に戻ってきた時には、すでに夜中になっていた。
セフィロスが予防線として連絡をいれていたから、特に咎められることはない。
万事抜かりのない英雄様だ。おまけにセックスは底なしだ。
性には全くの無垢。せいぜい児戯にもならない拙い自慰しか知らなかったクラウドは、骨の髄までアナルセックスを教え込まれた。
つい数十分前まで責められ続けていたクラウドはもうクタクタ。
痙攣を起こしそうな股関節を叱咤して、寮の自室へと急ぐ。
風呂はセフィロスの家で使ってきた。早く、とりあえず早く眠りたい。
固くて狭い自室のベッドが天使の寝床に思える。
でも、果たして眠れるのだろうか…
身体はセックスによって満足ゆくまで疲れ果てているが、心は別だ。
血が滾っている。クラウドも、男なのだから。
大きく息を吐いて、血の滾りを逃がす。
反応が遅れた。数名のシルエットがクラウドを取り囲みながら、施錠されている筈のトレーニングルームへと誘導していく。
神羅は原則として私闘は禁止だ。だがあくまでも原則としてのみ。
公になれなければ、かなり暴れても黙認される。
シルエットの持ち主にクラウドは見覚えがあった。
以前からクラウドに突っかかってきていたヤツらだ。
セフィロスの熱狂的な信奉者。セフィロスの傍に呼ばれるクラウドを本人達は認めたくないだろうが、妬んでいるのだ。
シルエットの数は正確には5人。どれもクラウドよりも逞しい体躯をしている。
「何か用?」
クラウドの血の滾りが牙を剥く。
「オレ疲れているから、早く休みたいんだけど」
挑発するべく婉然と笑う。
「−−神羅から出ていけ」
「サーにこれ以上近づくな」
「イイ気になりやがって!」
へえ、
「じゃ、オレに言わないで、セフィロスに直接言えば?」
「オレは神羅を辞めるつもりはない」
「イイ気にもなってないし」
「オレがセフィロスにくっついてるんじゃなくて、あっちが勝手に呼びつけてくるだけなんだけど」
トレーニングルームを何気なく見渡すふりをしながら、クラウドはチェックする。
施錠前に片づけられているのだろう。普段練習用の剣や銃器類やらは見あたらない。
あるのは、壁に掲げられているスティック。1メートルほどの長さのある実習用に使うものだった。
神羅にやってくる訓練兵たちは様々だ。モンスターの多い地方や戦争に巻き込まれたりして、有る程度戦いに慣れている者もいれば、全く平和でのんびりと暮らしてきた者もいる。
神羅に入隊すると銃の扱い方と共に剣術も教わる。剣術を教わる前段階としてこのスティックアクション、所謂棒術を習うのだ。
相手は5人。素手ではとても戦えない。
かと言って言われっぱなしでいるのは、血の滾っているクラウドには物足りない。
「コイツ!」
「サーを侮辱するなっ」
「侮辱してんのはあんたらの方だ」
「その女みたいな顔でサーをたらしこみやがって…」
セフィロスをたらし込むだって!?
そんな方法あったら、オレが教えて欲しいよ。
「本当にオレがたらし込んだって思ってるんだったら、あんたらもセフィロスの前で尻でも出してみれば?」
「…殺してやる」
怒りに目の眩んだ男達は、一気に詰め寄ってきた。
クラウドは持ち前の俊敏さで、身体を丸めて男達の足下をすり抜ける。
そして壁のスティックをとった。
「いいか−−」
「よってたかって大勢で、オレに当たるしか脳のないお前らはクソだ」
−−ファック。
奔放な金髪をよけて、つけられていたピアスを外す。
代わりに青い石のついたピアスをはめてやった。
つけて、眺めて、満足する。
クラウドの瞳と同じ青だ。形の良い耳にはこちらほうが映える。
「お前、寮でなにかやらかしたのか?」
さっきまで堪能した少年の肌には青黒い痣が残っていた。かなり薄くはなっていたが。
寮でなにがあったのか、セフィロスはすでに知っている。
すでに知っているのを解っていながら、クラウドはそっぽを向く。
「さあ、興味ないね」
原因が己にあるのをセフィロスは知っている。クラウドを構い過ぎるからだ。
クラウドだってそうだと承知しているにも関わらず、「あんたのせいだ」と訴えてこない少年を、セフィロスはとても気に入っている。
そう、とても。
少年は自分の耳にはめられたピアスへと触れた。
「返すよ」
「いや、受け取ってくれ」
「いらないよ…必要ないし」
それでも突き放した口調の割には、どこか照れているようだと感じるのは、この少年なりに歓んでくれているのだろう。セフィロスはそう判断する。
「お前がいらぬと言うのならば、捨てるしかない」
「…わかったよ」
ベッドから起きあがり服を探そうとする背中を抱きしめた。
途端暴れ出そうとする。
−−本当に面白い。
自分はきっとこの少年に飽きないのだろう。
例えそれが、己に剣を向けられた瞬間だとしても。